
(2012.10/31up)
江木健吉編up
追記部には下線を引く。
そもそもの発端は、とある女性の日記にある。
知人の母親の友人のお母さんの日記で、昭和5年(1930)に実際に書かれたものである。今、これをお借りして読んでいるのだ。彼女は別に有名人でもなんでもなく、たいした事件が起きるわけでもないのだが、戦前期のごく普通の市民の生活が見えて、妙に面白く読んでいる。
昭和5年(1930)といえば、日本史の中でも明治・大正時代と戦争時代というハデな時期にはさまれていて、あまりメジャーな時代ではない。おそらく、江戸川乱歩、黒岩涙香などの小説やその亜流で扱われる以外は、あまり知られていないのではないだろうか。だがちょっと調べてみると、世はまさに世界恐慌のまっただ中。翌年には満州事変。銀座ではモボ、モガが闊歩し、エロ・グロ・ナンセンスが流行っていた時代なのであった。この日記の書き手は当時山梨県に住んでおり、夫を亡くして女手ひとつで子供を育てている。
そのため東京市を中心とする最先端の流行に乗るということはないのであるが、当時活発であった自由主義運動には共感を覚えている。
ともかく日本が近代化していくまさにその時にいるのである。
日記というのは、特に人に見せることを意識したものではないので、本人にしか分からない事が当然あたりまえのようにさらりと書いてあるワケで、読んでいてもなかなか難しい。人名についても、家族知人関係が分からないのはあたりまえだが、時代が時代だけに時事ニュースに登場する人物もなんだかよく分からないものが多い。この日記の昭和5年2月22日(土)にこんな記述がある。
夕飯の仕度も出来たけれど子供が帰らないので一寸新聞を見せて貰ひに行くさてこの江木栄子とは誰だろう?と思った。
江木栄子女史が自殺した事があって総選挙の番狂はせなどより驚た
誰か有名人なんだろうかと思ってインターネットで検索してみたが、よくわからない。話の流れから、当時名を馳せた自由主義運動関係の人かなあ・・・とも思ったが、ともかく本屋に行った時に調べてみることにした。
『女性人名辞典』というのを開くと、ぱっと見たところ載っていない。やっぱりねと思って、ふと見返してみると【江木欣々】という名が目に付いた。中を読んでみると、この人であった。
えぎ きんきん 江木欣々 明治10年(1877)〜昭和5年(1930)ともかく数奇な人生を経た女性で、その生涯が小説のモデルになったんかな?と思ってちょっと調べてみると、鏑木清方は小説家ではなく、かなり有名な日本画家であった。「築地明石町」も彼が描いた美人画であり、見せられてみると、確かに見たことがある。そのままインターネットで思いつくままに、「江木欣々」「築地明石町」というキーワードで検索してみると、どうもひとくせもふたくせもありそうな人物がぞろぞろと出てきたのである。特に「築地明石町」のモデルは栄子ではなくて、妹のませ子であると分かってから、ガゼン面白くなってきた。
明治期の法律学者江木衷の妻。本名栄子。号を欣々、または欣々栄と称した。愛媛県令関新平の二女。東京新橋の美貌芸者として嬌名をはせ、間もなく衷と結婚した。詩、書、画、篆刻、謡曲と広い趣味と才人ぶりを見せ、社交界の花形となった。大正14年(1925)に夫と死別してから、寂しい晩年を送り、大坂の弟の家で自殺した。鏑木清方の名作「築地明石町」のモデルとして知られる。54歳。
【女性人名事典】
※0:
幕末〜戦前のつもりであったが、諸般の事情により幕末から20世紀末までがメインとなる予定。連載開始が2001年3月19日。で、今これを書いているのは2009年11月である。まだ終わりが見えないが飽きずに続けていることを褒めて頂きたい。まだまだ書かなきゃならないヒトが何人もいるのだ。
 |
彼女の双眼は、叡知のなかに、いたずら気を隠して、慧しげにまたたいていた。引き緊った白い顔に、黒すぎるほどの眼だった。もとより黒く墨を入れているのでもなければ睫毛に油をつけているのでもなく、深い大きな眼に、長すぎるほどな睫毛が濃かった。眉がまた、長くはっきりとしていて、表情に富んでいる。続いてませ子。
【近代美人伝/長谷川時雨】
ませ子さんも清方画伯が「築地河岸の女」として、いつか帝展に出品した美しい人である。(中略)ふと打ちむかった時、欣々さんにこうも似ていたかと思うほど、眼と眉がことに美しく、髪が重げだった。
【前掲書】
このふたりの父親は、佐賀の漢学者で尊皇派の志士として知られた関新平である。天保13年(1842)生まれ、佐賀藩士関迂翁の次男で、戊辰戦争の時、奥羽鎮撫総督府の使役として会津討伐に参戦したらしい。新平は明治新政府の司法卿江藤新平、東京府知事や民部・文部・司法卿を歴任した大木民平(喬任)と共に「佐賀の三平」と並び称された人物らしいが、後に言う「佐賀の七賢人」には入れられていないくらいなので、歴史に名を残したほどではないのだろう。この七賢人には、江藤、大木の他に、大隈重信(外務大臣)、副島種臣(外務卿)などがいる。実は佐賀の三平にしても、司馬遼太郎は江藤、大木ともう一人には、維新後品川県令となった古賀一平を挙げている。
関新平の父親はよく分からないが、佐賀藩に仕える官吏だったらしい。長男を早くに亡くし、次男の新平と、弟の清英の二子をもうけている。
 |
新任県令は県人を重用せず
さきに関県令入県後たちまち県官の更送あり、ために県民は何となく疑惑を生じ種々さまざまの浮説あり、また県官は何ゆえにや概して県人を擯斥せらるるがごとく、勤め続きの官吏は過半他県人なり、また新任の属官はおおむね地方事務に暗く、従って事務の捗りかぬるより、人民は我が県人は未熟なる官吏の草紙とせらるるようになりてはたまらぬなどと、ひそかに不平を唱うるものもありとか。かつて県下にて三部長の聞えありし松本實四郎、小林信近、郡築温の三氏はすべて先に辞職し、長屋忠明氏もまたさきに辞表を出されたりとか云えども、未だ指令あらず、或いは云う、同氏は過日令公へ一篇の忠告書を呈せられたるが忌諱に触れ、何にか尋問中なりと噂あれど、その信偽を知らず。
【朝野新聞/明治13年8月24日】
岩村県令は一度地方官会議からは帰県されたが、在京中にモウ内々の話しも済んでたのであったろう、政府から、内務省の戸籍局長に転任を命ぜられた。我が県の主立った市民は民権主義であったから、人望も同氏に帰していたので、この転任は非常に失望したけれども仕方がない。(中略)関新平も茨城県時代は士族授産に努力したり、明治7年(1874)水戸城火災の嫌疑を受けた人々の無実を晴らしたりする(※1)など評判は悪くなかったらしいが、結局関新平は旧幕藩体制の古い因習が抜けきっていなかったのかもしれないし、県令という地位がそうさせたのかもしれない。記事中の公共社は松山の民権結社であるが、ここの井手正光は関新平をこう評している。
今回県令の更迭は今もいう如く岩村氏が民権主義に傾くという事からであるから、新来の県令は漢学者で保守主義である。関新平氏というのが拝命された。この人は佐賀人でこれまでは茨城県令をしていて、水戸人とは気風が会っていたから、この度の転任と共に茨城県人を数人連れて来て、課長や重なる県官の椅子は段々とそれらに与えた。そうして今まで岩村氏に親しかった者は氏の斡旋で内務省へ転任した。(中略)一体岩村県令の民権主義を最も賛成して、その他常に出入りをして県令と親しかった者は我松山人なので、その訳から皆転任せしめられたのである。
【鳴雪自叙伝/内藤鳴雪】
「正直な漢学者で酒を好み、西洋流儀の議論をすると激昂、孔孟主義で論じると機嫌がよかった」関新平は明治20年(1887)3月7日、愛知県令在任中に亡くなっている。彼の業績として、高知・徳島両県令に呼びかけて計画を立案した松山−高知−高松を通す四国新道開削が挙げられる。新平は完成を見ずして亡くなったが、愛媛県柳谷村川之内に業績を称えた碑が建てられている。
関新平の父親関迂翁についてはほとんど資料が見つからない。『佐賀先哲叢話』によれば国学派であり、儒学中心の藩の中では少数派だったようだ。しかしその思想が関新平に受け継がれているのはまちがいないだろう。
先生名は清泰、通称は判蔵、号は迂翁、明治七年六月に歿せられた。年は六十三であった。
先生は初め国学に入つて居られたが、後、京都に遊学されて、猪飼敬所と云ふ人に就いて、経学を修められ、帰国後、教諭になって居られた。併し先生は古学を奉じて居られたので、其の説、往々藩の儒者達に入れられず、遂に辞職して官吏になつて居られた。
【佐賀先哲叢話】
※1:
水戸偕楽園に関新平の遺徳碑が残されている。
 |
ところがどうやらこれは正式な結婚ではなく、「おてつき」だったようである。関がまだ16歳の女中花子に手を付けたというのが真相らしい。関新平は当時、神田駿河台に居を構えた大審院判事であり、故郷の佐賀に妻の和気子と娘の悦子を置いて来ていた。田舎からぽっと出てきた権力者の主人と、出入りしている旧商家の娘という、なんだか時代劇にでもなりそうな設定だが、ともかく栄子は庶子としてこの世に生を受けた。そのため栄子は物心つくまえに、京橋区木挽町の古道具屋(一説によると高井戸の農家)に里子に出されてしまう。
「あたしのように血縁のものに縁の薄いものがありましょうか、あたくしの母は、十六歳であたくしを生んだといいますが、物心づいてからは、他人に育てられましたのよ、だから、生の母にも逢わずに死なせ、その実母の父親――おじいさんですわねえ、その人は、あたしが見たい、一目逢いたいと、それだけが願望だったというのにこれも隔てがあって逢わずに死なせてしまいましたわ。実父の家とは、父の死後に、義母姉妹の交わりをするようになりましたけれど――」ませ子が生まれたのは明治19年(1886)のことだが、花子は栄子を孕んですぐに家に帰されており、栄子もまた生後一年ほどで養子に出されたので、栄子とませ子の面識はない。栄子も生みの親とも認識する前に養子に出されたことになる。ませ子とも後に再会を果たすまで、お互いの存在すら知らなかったのである。
【近代美人伝/長谷川時雨】
妾(わたくし)は物心付始まる十六歳の時に人妻になりましたで御座いますから妾の娘時代は其様考へは少しもなく只もう遊ぶ事と人形を買て貰ふことが一番好きで人形にお芋を食べさして喜んで居たものですしかし不幸なことにこの旦那も1年あまりで病没、有吉家を出されて、栄子は再び花柳界に戻る。今度は新橋に移り、松屋という所から、改めて「ぼたん」という名で半玉として出ることになる。
【『娘問題』妾を教育したのは良人です/江木栄子談】
ちなみに半玉というのは、簡単にいえば芸妓のたまごで、芸妓の玉代が一本のところ、半分なので半玉という。京都では舞妓という。
江戸期までの東京の花柳界は吉原がトップ、次に品川という明確なランクがあったが、維新により新橋・柳橋が遊興街として急速に台頭してくることになった。これは維新により旧幕臣、旗本が支配階級を追われ、幕末には三流と言われていた新橋・柳橋界隈で遊んでいた勤王党の志士たちが、政界に躍り出たからである。花柳界といっても現在の風俗界のようなものというイメージではなく、大正くらいまで食事と遊びがついた一種の社交の場であった。
当然ランクがいろいろあり、町民が遊ぶ所と、政治家が政談等に使う場所は全く違う値段と雰囲気があった。現在で例えていえば、銀座・赤坂が政治にも使われる高級な遊興街、新橋・上野が下々のオジさんたちがたむろするところ、といった感じである。従って花柳界、芸妓といっても、必ずしも売春婦を意味するものではない。かえって技芸に優れ、頭がよく教養があり、様々な話題にもついていけないと、優れた芸妓とは呼ばれなかった。
田舎者の勢力に依つて、次第に発展して来た新橋の温柔郷が、今日でも実業家、政治家、官吏を主な得意として、第一流の存在でありながら、何処かに田臭を漂はせて居るのも、争はれない因縁でせう。第一流の名妓と云へば、多くは名古屋、新潟、秋田の産であり、客も芸妓も新橋は、今や田舎者に依つて、何も彼も征服された形であります。
【銀座/松崎天民 昭和2年刊】
当時は芸妓の時代であり、明治の元勲たちも多く芸妓を正妻としている。伊藤博文(梅子)、原敬(浅子)、板垣退助、犬養毅(千代子)、山県有朋(貞子)、陸奥宗光(おりう)、木戸孝允(幾松)なども皆、元芸妓を正妻に迎えている。うがった見方をすれば、維新により薩摩・長州・土佐・肥前など地方から大挙して訪れた元・志士たち、ようするに田舎侍たちを、偏見なく見ることのできたのは、芸妓くらいだったのかもしれない。それも吉原とか格式高い所(つまり旧幕派)ではない新興遊興地区の芸妓たち。
当時藩が違えば外国という程の認識がある上、訛りも強く、江戸っ子のように粋な遊び方ができなく、そのくせ自分たちの上に立って偉そうにしているというわけで、江戸っ子としての矜持のある東京の町民から嫌われたという記録もある。元々は刀を担いで風雲の中を走りまわっていた気の荒い浪人どもである。この人材を使って明治政府の政治家や官僚が大量生産されたのであり、その地方侍が大挙して東京になだれ込んできたわけである。維新は政治界だけでなく、東京花柳界の勢力地図をも一気に変えたといえる。
ともかく、これが一種のブームとなって、大正時期までしばらく、政治家や有力者が芸妓を正妻に迎える風習がついたのである。
この新橋芸妓時代に栄子は、当時の売っ子法律学者、江木衷(まこと)と出会い、結局栄子は衷と結婚し、正妻におさまることになる。おそらく明治30年(1897)代初めころのことで、衷が40歳初め、栄子が20歳ころというから、20歳も年が離れた夫婦であった。
江木衷と結婚したことにより、栄子の生活は一変する。衷は当代随一並ぶものなき敏腕弁護士であり、顧客・知人も政財界のトップクラスである。栄子はここで社交界デビューを果たし、夫の権勢もあったであろうが、芸妓時代に身につけた玄人はだしの諸芸の巧みさと、類まれなる美貌でもって、一躍社交界の花形となってゆくことになる。
※2:
栄子の生年については、ほとんどの典籍は明治10年を採用しており、当時の新聞雑誌や上記の「女性人名事典」もそれを採用している。しかし栄子の墓誌が明治12年生となっているため、本文ではこちらを採用する。
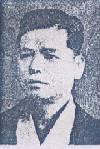 |
そもそも日本の法学界は完全に二分しており、政府司法省系のフランス法派と、大学を中心とするイギリス法派が対立していた。司法省は箕作麟祥が翻訳したフランス法をベースに、ほとんどフランス民法の丸写しの民法を作るなど、フランス法万能的な考え方であったが、衷が卒業した東京開成学校を始めとする大学法学部では、初期からイギリス法学を教授しており、これを卒業した官僚・法学者はイギリス法を信奉していた。ここにフランス人の編纂した民法(明23)とドイツ人の編纂した商法(明25)とが発布される。これにイギリス派が真っ向から反発したのである。この宣言書はもう喧嘩を売っているに等しい。
一 新法典ハ倫常ヲ壊乱ス。外国の治外法権撤去のために法典の整備が急がれていたという事情があったらしいが、この論争は学会のみならず、議会やマスコミを巻き込んだ一大論争となった。結局この争いはイギリス派が勝ち、施行を延期して見直しということになったのだが、面白いのは江木衷が、こういうものは純粋な学問的正当性よりも、議員や世論を味方に付けた方が勝つということを知っていた事である。
一 新法典ハ憲法上ノ命令権ヲ減縮ス。
一 新法典ハ予算ノ原理ニ違フ。
一 新法典ハ国家思想ヲ欠ク。
一 新法典ハ社会ノ経済ヲ攪乱ス。
一 新法典ハ税法ノ根原ヲ変動ス。
一 新法典ハ威力ヲ以テ学理ヲ強行ス。
激烈な論争駁撃の場合に、法典の法理上の欠点を指摘するなどは、白刃既に交わるの時において孫呉を講ずるようなもので、我ながら迂濶千万であったと思う。要は議員を動かして来るべき議会の論戦において多数を得ることであった。その目的のために大なる利目のあったのは、延期派の穂積八束氏が「法学新報」第五号に掲げた「民法出デテ忠孝亡ブ」と題した論文であったが、聞けばこの題目は江木衷博士の意匠に出たものであるとのことである。双方から出た仰山な脅し文句は沢山あったが、右の如く覚えやすくて口調のよい警句は、群衆心理を支配するに偉大なる効力があるものである。
【法窓夜話/穂積陳重】
さてこの法典実施延期戦において江木衷は、衆議院に提出する理由書を書くことになったが、衷はそのまま雲隠れしてしまう。期限は迫るが依然衷は姿を見せず、周囲がやきもきしはじめたころ、衷が実は向島の料亭で酒池肉林の乱痴気騒ぎをしているのが発覚する。
而かも其実は一杯一箸、悉く彼れが霊腕妙想を誘ふの好材料となり、頓て其想熟し、その機達するや急に筆を呼んで、一揮奔電の如く、頃刻にして草案乃ち成る、公明の事理、行ふに謹厳痛切の文字を以てし、一句泛ならず、筆に真理を蔵す。彼の帝国議会に上れる有名なる法典延期理由書は即ち是れにして、此理由書は実に冷灰雲隠れ中の産物たりしなり。同志の此案を提(ひっさ)げて天下に呼号するや、賛成派亦た起って反対の声を大にし、政治舞台の争は、更に法曹社会の戦となり、明治法律学校(今の明治大学)一派は遂に法治協会なる者を組織して、盛に英吉利法学派に対抗し、和仏法律学校(今の法政大学)の一派亦た之れに応援して、盛んに延期派と鎬を削りぬ。然かも延期派は遂に捷(か)てり、蓋し冷灰の文、与って最も力あるもの。国立国会図書館に、江木衷から井上馨に宛てた手紙が残っている。日付不明なのだが、想像をたくましくすると、この法典実施延期戦の時に書かれたもののようにも思える。いずれにせよ江木衷の性格がよく現れているので、ここに掲げておく。
【近世法曹界逸話】
意見書公表ヲ決意 印刷出来一両日中ニ供覧 先輩ヨリ過激ノ注意ヲ受ケシモ之ニヨリ免職処刑モ本望衷はその後内務省を経て外務省の参事官を務め(※3)、御雇外国人デニソンと共に大隈重信の条約改正案撤廃に尽力している。「官界の驕児」と異名を取ったというから、政治家の都合なんて委細構わずかなり好き勝手やったらしい。第一次松方内閣の内務卿、品川弥次郎(※4)の秘書官として、選挙干渉のため地方に出張した際、報告がわりに都々逸を電報で打って済ませたというエピソードが残っている。
然るに此振出しが既に話柄を残して居る、先づ警視庁へ採用になるから履歴書を出せといふ。衷は之を出したが生年月日を書いていない、そこで之を書けと命ずると二十七歳位と書いて出すから、
○二十七歳位の位は可笑しい何年何月何日と書きなさい
□俺は生まれた年月日は知らない
○自分の生まれた年月日を知らないものもあるまい
□いや自分で何時生まれたか覚えがない
○誰だって自分の生まれたのを覚えて居るものはない親から聞いたらう
□勿論親から聞いたがそれは人のいふことだから当にならない(※5)
此返答には係りの者も呆れ果てた、衷もまた没分暁(わからずや)の奴等の居る処だと呆れて間も無く司法省へ出て検事となり参事官となった、此参事官時代に各地方から色んな報告が来ると衷は一見してこんな馬鹿なことを書いてあるとて残らずストーブへ叩き込んで灰としてしまった、冷灰の語之れより起るといふのでは無いが、兎に角痛快な男であった。
【法曹珍話閻魔帳/尾佐竹猛】
この品川内相の秘書官を最後に官を辞し、明治26年(1893)に弁護士法が制定されたのを機に在野に降り、同年2月11日、日本橋蛎殻町三丁目に弁護士事務所を開業する。
原嘉道呼出シ説諭セシモ決心動カシ難シ 江木辞表ノコト取計イ乞ウ 阿部浩
【明治26年3月31日付井上馨宛陸奥宗光書翰】(※6)
江木衷氏、一昨日内務省参事官を辞職せる同氏は、代言業を営む筈にて近日出願するよし弁護士としての初めての仕事は、三井三池鉱山に関する有名な民事訴訟裁判であった。大蔵省より三井に払い下げられた三池鉱山が地震で損害を出し、三井がその損害を大蔵省が負担するように求めた裁判である。一審二審は三井の勝訴となったが、大審院で逆転判決が出て、敗訴している。
【時事新報/明治26年2月5日】
衷はその一方で風流を解し、自らを「冷灰」と号して漢詩を書き、森槐南(※7)らと共に一詩社を設けて独特の詩風を興している。秋山定輔(※8)の反権力新聞「二六新聞」の発起人に名を連ね(明26)、大陸問題を論じる江湖倶楽部を組織したり(明31)するかたわら、世人向けに筆を執り、鋭い舌鋒で政府・司法界・教育・世相をこきおろしてヤンヤの喝采を浴びた。長谷川時雨はその文章を「風流にことよせて、サッと斬りおろす(中略)該博な、鋭い切れ味」(近代美人伝)と評している。
多言繋称(はでやか)、連レ類(すぢだて)比レ物(たとへごと)すれば虚而無レ実(ほらをふく)とおもはれ、総レ微説レ約(かいつまんで)径省(みじかく)而不レ飾(ぢみにす)れば吻而不レ弁(くちがきけぬ)とおもはれ、人情を説けば僭而不レ譲(ですぎもの)とせられ、妙遠を論すれば夸而無レ用(からいばり)とせらる。固と是れ古今の通弊。陳腐漢(ちんぷんかん)の口真似するまでもなし、かくて有罪の判決は下らん。可憐(あわれむべし)百日の説法屁一つ、馬鹿々々しき限なれど、唯只判官は自ら其信ずる所を行ふのみ。知らず/\無罪を有罪とするのみ。(中略)いつも煙草をくわえている重度の愛煙家で、なおかつ大酒を好み、辛辣かつシニカルで諧謔的な性格であったらしいが、その反面派手好きで開けっぴろげで面倒見がよく、ユーモアを解した人物であった。
司法界の現状に視て常識裁判所を設置せんとするは空中に楼閣するなり。法官に向って世態人情を学べと詆責するは石仏を灸熨するなり。(中略)然らば則ち此空想以外、此寓言以外、如何にして此時弊を救済し得べきか。如何にして常識の欠乏を補充すべきか。曰く陪審制度新設の一時あるのみ。常識を備へたる常人をして司法裁判の大権に参与せしむるの一事あるのみ。常識欠乏を前提せる論理の論結之を人間社会に実現し得べきもの唯是此一事。
【冷灰漫筆/江木衷】
江木氏は有名な酒豪であると共に又非常な煙豪である。「ヤア、マア風呂へでも這入り給へ」と初対面の人でも何でも平気で一緒に風呂へ這入りパクリパクリと五六本平げる。寝床便所で喫ふのを合算すると葉巻で一日廿本位敷島なら十五六箱だらうと云ふ評判で時々「静岡降りに付 着駅致し候はヾ御起し願上候 車掌殿」などと云ふ札を貼り付けて汽車中でグウグウ高鼾なぞの奇芸もやる実兄に枢密院顧問官となった江木千之(かずゆき)、甥に法相、鉄道相を歴任した江木翼(たすく)がいる。華やかな才能あふれる一族であったらしい。
【大阪パック】
※3「岩村脳病前田ハ得意 江木衷サスガハ山口県人岩村ヲ見限リ外務省ニ去リ今後オ引立テアレ」(明治23年2月1日付井上馨宛古沢滋書翰)
※4 品川弥二郎:
幕末長州藩の志士で、吉田松陰の松下村塾出身。文久2年の寺田屋事件に関係、後、高杉晋作らの御楯組の血盟に参加。京にあって木戸準一郎らと薩長同盟の実現に尽力した。維新政府の農商務省、駐独日本公使、宮中顧問官、御料局長官、内務大臣、枢密顧問官を歴任する。
※5
冷灰『お前は何月何日生れだと聞かれて、某月某日と答ふるものゝ気が知れぬ。誰れだって、自分の生れた時を知ってゐるものはない。自分で知らないものを返詞が出来る筈がないぢゃないか』【「江木冷灰の言葉」日本及日本人/大正14年5月1日号】
※6 原嘉道:
慶応3年信濃国生。帝国大学を卒業して農商務省に入るが、明治26年に退官、江木忠と同様弁護士となる。農商務省では、大臣陸奥宗光やその秘書官原敬に目を掛けられた。後政界に転身し、昭和2年田中義一内閣の司法大臣。
阿部浩:
嘉永5年盛岡藩生。盛岡藩では原敬の先輩であり、群馬・千葉・富山・新潟・東京府などの知事を歴任。
※7 森槐南:
明治期の古注学者・漢詩人。宮内大臣秘書官、式部官を歴任。伊藤博文がハルビンで暗殺されたとき、随行していて負傷した。
※8 秋山定輔:
朝鮮問題や大陸動向に注目した独立系政論新聞「二六新報」を明治26年に発行。経営難のため、1年余りで休刊となるが、33年に再刊する。一時は黒岩涙香主宰の「万朝報」を抜いて、一時、東京で最も売れる新聞となった。
衷の父親は、江木俊敬(幼名佐次郎または佐仲次、通称仙右衛門)という名の幕末の周防岩国藩吉川家の家臣である。村上源氏の流れをくみ、武田家、毛利家、吉川家、広家に代々仕えた家系であるが、鉄砲組十五石の江木繁憑(通称仙左衛門)の嫡男として生まれているので、位は低い。しかし長州藩の前原一誠(※9)の知遇を得て国事に奔走するようになったが、その中で藩主の目に留まり、藩のために働くようになった。幕末の岩国藩主吉川経幹は、藩校養老館を開設して広く人材を集めた開明的な藩主であり、その関係もあり登用されたものであろう。
そもそも吉川家は毛利家の分家であるが、関ヶ原の戦いの時、西軍と宗家毛利家を裏切って徳川方に内通し、軍を動かさなかった。その東軍を勝利に導いた功により、防長二州を与えられたが、それをすでに改易の裁定の出ていた宗家毛利に譲った。しかし毛利本家からは家を売った裏切り者として疎まれ、この確執から江戸時代を通じて岩国藩吉川家は大名とは認められず、長州藩の支藩扱いであり、両者の関係も疎遠になっていた。
しかし幕末に至り、長州本藩が尊王攘夷の方針を固めた頃より関係が修復し、岩国藩主吉川経幹も文久2年(1862)宗家毛利敬親の名代として上京し、河原町通姉小路の京藩邸で朝廷工作に奔走していた。俊敬は万延元年(1860)に一時岩国藩を離れていたが、文久2年には岩国町奉行に戻っていた。翌3年には藩主に従って京都に同行していたようである。
岩国藩が京都護衛の任にあたっていたとき、堺町門の変が起こる。幕府と薩摩藩が密かに手を結び、京都から長州一派を追放したのである。この時尊王攘夷派の三條実美卿ら7人の公家が夜半をついて京都を脱出(いわゆる七卿落ち)し長州に落ち延びるが、この時俊敬は銃士38人を率いて藩主や久坂玄瑞らと共に、七卿の護衛にあたっている。
元治元年(1864)、関門海峡を通航する外国船を無差別に砲撃していた長州藩攘夷運動への報復として、英米仏蘭四ヶ国艦隊が下関砲台に攻撃をしかけた時(下関戦争)、俊敬は戦場監察の任についていたが、退却しようとする軍に反対して主戦を強調、受け入れられないとみるや自ら従僕1人を引き連れたのみで馳せ参じ、3日にわたって戦闘に参加し、自ら3発の銃弾を受けている。帰藩後藩主に戦況を報告し、この功により感状を与えられている。
右先達而より馬関詰として差出置候処、此度夷船襲来、陣屋出張相成、追々戦争に及候に付ては、見分万事行届、猶又引取の節は気付の廉、戦士方へ委曲申置候儀も有之、且途中より早打を以て罷帰り注進せしめ候段、忠節を考へ彼是抜群骨折候段、神妙の至に候云々【重見熊雄/江木俊敬奉公事蹟】この戦いで長州藩は外国艦隊に赤子の手をひねるようにやられてしまい、攘夷派が失速、さらに幕府の長州征伐への動きも始まる。このため藩内は幕府恭順の俗論党勢力が主流となる。しかし尊皇攘夷を唱える正義派高杉晋作は慶應元年(1865)奇兵隊を率いて決起し(功山寺挙兵)、俗論党を武力で一掃すべく萩城へ迫る。それに対抗して萩藩毛利政府は正義派諸隊の追討令を発する。岩国藩では隣藩徳山藩の動向を見た上で対応することに決め、元治元年(1864)大晦日、徳山藩の内情を探るために俊敬を派遣する。俊敬は徳山からの帰藩途上、玖珂阿山で敵の間諜と誤認され、藩議を待たずに出兵した味方先鋒隊の羅卒に惨殺されてしまうという、少し情けない最期を遂げた。元治2年(慶應元年)1月13日歿。42歳であった。
心は矢の如く、途を急いで漸く岩国藩領に入つたが、何ぞ図らん、是より先に、藩議は父の復命を待たずして出兵を決し、其先鋒たる警邏の一隊は、早く已に此地に在つたので、忽ち其誰何する所となつた。父は直に告ぐるに氏名を以てしたが、士卒等狼狽して一意に父を以て敵諜と誤認し、隊長某は馬上自ら鉄槍を挺して身辺に迫り、部下の兵卒も亦争ふて其下に集まり、事極めて急となった。これに先立つ元治元年12月31日夜、徳山への偵察命令が出されると、俊敬はこれが家族の顔を見る最後の機会と覚悟したのだろう。妻と惜別の酒を酌み交わし、三人の子供を膝下に集め、訓令している。
父は敵諜ならざることを証せんとし大声名乗りを揚げ、且つ懐から人馬帳を把つて之を軍中に投じたけれども、士卒周章狼狽して之を顧みるの暇なきものゝ如くあつた。而かも父は対手の友軍たるを知つて居る。唯だ之を避くるの一途あるのみである。
事益々急なるに及び刀を揮ふて且つ防ぎ且つ退くこと数町であつたが、終に乱刃の下に斃れた。実に元治二年正月十三日の夜半であつた。
軍兵等父の死体を検して、始めて父なることを知り、其の懐を探りて緊切なる報告書を発見し、急ぎ之を藩庁に致し、藩の行動を決するの資料に供したのである。為に父の国難に殉じた誠忠の事情が始めて明瞭となり、特に藩主の命に依つて横山龍門寺に埋葬せられた。同寺は三百年来藩主が親しく臣下の忠死を弔はるる菩提所であつた。
【江木千之/母を懐ふ記】
「わが家は地位も低し、禄も僅かであるが、然し三百年来藩に仕へて居るので、地位の高下や禄の厚薄に関せず、一意に藩の為め、国の為めに尽くさねばならぬ。父が七卿を護送して王事に尽くした事や、馬関の攘夷の戦争に勇戦して感状を戴いた事などはお前達の既に知る所である。お前達も大きくなつたら、自分一身の利害を考へずにお国の為めに尽くさねばならぬ。徳を修め、武を励みてお国の御用を勤めねばならぬ。」俊敬は自らが戦った成果を見ることなく歿れた。維新という将来を見据えていたというより、他の多くの人たちのように、ただ藩のために尽くしただけなのかもしれない。下級武士でありながら、あるいはだからであったからこそ、藩の命運に自らの全てを賭けられたのかもしれない。彼もまた幕末の動乱に翻弄されたひとりである。
【前掲書】
高杉晋作のクーデターにより長州藩の方針は再び倒幕に纏まり、その後岩国藩は長州藩と共に幕軍の第二次長征を戦い、勝利して官軍となる。
藩主吉川経幹もまた慶應3年(1867)病没しているが、宗家毛利敬親の斡旋により、慶應4年(明治元年)入封以来268年目にして岩国藩は大名に列せられることとなった。廃藩置県までのたった3年だけの大名であった。
江木俊敬のお墓は、下関の西福院と山口二島朝日山にある。死後50年を過ぎた大正9年、靖国神社に合祀され、従五位を贈られている。
俊敬の妻、衷の母親についてはあまりよく分からないが、長男の千之が『母を懐ふ記』というものを残しているので、それと墓誌などの情報を元に、かいつまんで記してみよう。
彼女の名は糸子と言い、旧姓は田村である。文政6年(1823)生まれで、俊敬の1歳年上にあたる。長男の千之は30歳過ぎての子ということになる。慶応元年(1865)に俊敬が亡くなった後、家は没落していくが、長男千之に家督を継がせ、子供を三人抱えて家を守るために奔走する。千之は当時13歳で、幕末の動乱のまっただなかであったが、子供達に士道を教え、借金しながらも息子たちに刀をあつらえてやるなど、相当苦労はしながらも、武士の妻としての役割を果たしたようである。長州征伐の間には、千之を戦に出し、衷とその弟に手伝わせながら硝石を製造したり、泣きながら帰ってくる千之を叱咤して送り返したりしている。清貧に暮らしながらも息子3人を立派に育て上げ、息子千之が政治家になると、それに付いて東京に出たようである。明治29年に胃を患い、子供らの成功に満足して「死して恨む所なし」と言い残して10月14日に亡くなっている。享年74歳。谷中墓地に葬られる。栄子の姑にあたる関係であるが、没年から見て会っている可能性はない。
俊敬と糸子の間には三人の子がおり、長男が吉太郎(千之)、次男が衷、三男が精夫という。俊敬亡き後、江木家の家督を継いだのは吉太郎である。父が憤死した年、吉太郎いまだ13歳、衷はわずかに8歳、精夫は5歳であった。
※9 前原一誠:
萩藩士。松下村塾の門下生。
高杉晋作らと共に俗論党討伐に決起した。四境の役では小倉口参謀。戊辰の役には北越征討督府参謀。平定後、越後府判事、兵部大輔。
下野した後、萩の乱を起こし捕らえられ斬首。
 |
動乱時代は過ぎ去り、開国後の日本では、剣に代わって西洋の新しい知識が立身のための武器となった。猛勉強して新しい知識を貪欲に吸収した千之は、明治7年(1874)22歳の時に文部省に出仕する。十三等出仕というから大抜擢されたわけではない。木戸孝允(桂小五郎)が台湾出兵に反対して辞職した直後であるが、なんらかの長州閥の人的繋がりがあったのかもしれない。千之自身のちに、「東京に縁故のある者はツテを求めて郷里を後にしたが、ほとんどが官吏となった。」と言っている。それくらい長州の藩閥は強かったということであるが、ともかく千之は省内で参事官まで出世する(明24)この文部省時代に小学校教員心得、同教則綱領などの起稿に貢献したらしい。
また、この文部省時代に弟の衷を東京に呼び寄せ、自分の給料を出して学業に就かせている。
明治25年(1892)、長州閥の長老山県有朋の薦めもあって内務省に転じて県治局長となり、日韓連合、帝国憲法草案、占領地行政規則の起草など、少しキナ臭い仕事に携わる。
明治29年(1896)茨城県知事に選任。これは「生きた人間を相手とする地方の小政府を統轄してみたいし、面倒な所の方が面白かろうし、またかつてから水戸学を崇拝していた」(江木千之翁経歴談)と言っているように、自ら望んで行ったものである。茨城県では利根川水害の復旧工事を手始めに農商工業の振興に力を入れ、民権派からも絶賛されている。しかし千之は明治29年末にチブスに罹り入院する羽目となり、退官するつもりでいたが、当時の内務大臣樺山資紀より栃木県転出を要請される。当時栃木県では足尾銅山鉱毒事件に揺れており、その政治手腕を見込まれたためである。千之が栃木県知事に在任したのはたったの7ヶ月であったが、災害復旧や県議会との融和に力を尽くしている。千之はその政治手腕をかなり見込まれたトラブルシューターだったらしく、この後も築港問題で紛糾していた愛知県知事に命ぜられ、その後も広島・熊本県知事を歴任、明治37年(1904)には貴族院議員に勅撰されるなど、順調に出世を果たす。
しかし40年(1907)大病を患って右足を切断。同時に熊本県知事を辞す。その後は貴族院議員として活躍し「爾後議政壇上に謇々諤々の論陣を張り歴代内閣の一苦手たり」(人名大事典)
大正13年(1924)、清浦奎吾内閣に文部大臣として入閣。同時に文政審議会を創設して副総裁に就任するが、この内閣は5ヶ月という短命で瓦解する。その後は枢密院顧問官となり、在任9年目の昭和7年(1932)8月22日歿。享年80歳。娘がひとりいたが、家を継ぐ男子に恵まれなかったため、翼を婿養子に迎えている。
これら政・官界と併行して、防長教育会、教育調査会、大東文化協会、皇典講究所及び全国神職会、日本赤十字社などにも尽力した。
再び『人名大事典』の手放しの賛辞によれば、
「資性英敏剛毅にして識見高邁、己れを持する質素謹厳、意を風教の維持に留めた。」
江木千之の妻は中子といい、季刊『海堡』によれば、同じ岩国藩出身の西田明則の養女である。西田明則は文政10(1827)年、岩国藩生まれで、錦帯橋の修理に携わった祖父を持つ藩の普請方・測量方であった。千之は岩国藩時代、彼に語学や数学を学んでいる。西田明則は維新後は兵部省に出仕して工兵大尉となり、東京湾防衛のために建設された東京湾海堡建設に多大な貢献をした。明治39年(1906)没。
さて恩師の養女を娶った千之であるが、ふたりの間には明治15(1882)年、秀子という女の子が生まれているが、男子には恵まれなかった。秀子は東京女子師範学校付属高等女学校(現御茶ノ水女子大学)を卒業する才媛であった。体も弱く、千之はこのひとり娘をかなり可愛がったようであるが、その育て方は厳しくもあった。優しく、また生真面目な娘であったようだ。
江木家の三男、精夫についてはあまりよく分からない。千之の自伝を読むまでその存在に気付かなかったくらいなのだ。彼は文久1年(1861)生まれで、日露戦争に従事した陸軍軍人であったらしいが、詳しい来歴が見つからない。ただ旧日本陸軍の士官学校卒業生について書かれた『市ヶ谷台に学んだ人々』という本の旧制師範学校5期生の項にその名が見える。
江木は陸大中退、日露戦争当時は歩兵少佐で北京にいた青木大佐の特別任務班の情報班長として活躍、その功績によって殊勲甲の金鵄勲章功三級を授与された。この青木大佐なるものが何者かと調べてみれば、当時中国にあった公使館付武官を務めた男で、対中工作を実施する特別任務班の親玉であったらしい。その任務は「電信線の切断、鉄橋の破壊、馬賊による牽制行動などの後方攪乱工作と、情報収集の諜報工作がその主たる活動内容であった」(戸部良一/日本陸軍と中国)というので、ようするに精夫はスパイの親玉だったのである。日露戦争の特務機関といえば、ドイツでロシアの後方攪乱任務を行っていた明石元二郎が有名であるが、その中国版が青木大佐の特務機関である。
(中略)
この両名(註:江木と荒尾)こそ一身の栄達よりも国事を優先した真の国士と言えよう。
【桑原嶽/市ヶ谷台に学んだ人々】
その後の調査で戦時中の活動が少し分かったので追記してみたい。谷壽夫中将(この人は南京大虐殺の主犯のひとりと言われた人)が書いた『機密日露戦争史』(原書房)に、江木精夫の活動について触れられている。これによると、陸軍参謀本部の場当たり的な組織改編に振り回されている様子が見える。
そもそも日露戦争当時、日本は中国やロシアについての地政的情報が皆無に近く、また情報活動も原始的なものでしかなかった。その中心は、外国公使による外務省経由の情報の他、陸海軍から独自に各国へ派遣された公使館付武官が情報収集にあたっていた。先に名を挙げた明石元二郎は陸軍参謀本部よりロシア公使館に遣わされた陸軍武官である。同様に中国(清国)や韓国へも武官が派遣されている。
日露戦争開戦時の陸軍参謀本部は5部で構成されており、そのうち第一部は松川敏胤大佐が率い、第二部は福島安正少将が率いていた。しかし当時の参謀本部では作戦担当と情報収集が分担されておらず、明治32年(1899)の組織変更から、第一部は北方面の師団を管轄し、アジア方面の情報収集を、第二部は南方面の師団を管轄、英米アフリカ等の情報収集担当と、地域別の配置となっていた。
江木精夫は、松川敏胤と陸軍士官学校第5期の同期であり、その縁もあってか、松川大佐の参謀本部第一部の情報担当として京城(現在のソウル)に派遣される(精夫は中佐に昇進している)。
しかしややこしいのは元々情報担当であった福島少将の第二部も中国に情報拠点を持っており、満州や韓国を含む大陸地方の各地に第一部系の第二部系の2系統で派閥を作りながら情報活動を行っていた。松川系の派閥に属すると思われる谷壽夫によれば、そのココロは、
而してその派遣の真因は、従来の情報将校が自ら諜報勤務に任ぜずして、多くは清韓人を使用せるため、適確なる情報を得ざるのみならず、これら情報将校の大部は戦術上の判断力なきため報告概ね要を得ざりしに基づくと、あわせて第二部に露国通なかりしに因るものということである。その第一部の尖兵として送り込まれたのが江木精夫である。情報系統が2系統で派閥があるということは、当然両陣営間の反目もあったようである。まあ、あまりにも日本的な派閥関係、という感じがする。しかし実際江木精夫は、中退はしているものの陸軍大学で2年学んでおり、他者より質の高い情報報告をしたらしい。この本でも、極東方面での情報では、江木中佐のものがピカイチだったと書いている。
日露関係が風雲を告げる明治37年(1904)正月。精夫は一旦日本に帰り、参謀本部児玉源太郎次長より「北方より増加する敵兵力を偵察し適当の方法にて報告すべし」との命を受ける。精夫は土井市之進大尉を引き連れて、1月2日に東京を出発する。
参謀本部 臨第二五号第一門司から船で泰皇島に上陸、そこから北京に入る。ここで禅宗の僧黒禅を雇い、2人はその弟子に変装することとする。まず通訳として雇い入れた森脇源馬と黒禅を先発させ、精夫と土井大尉が遅れて1月19日北京を出発、24日に溝幇子に至る。先行させた黒禅の報告がなく、また、ロシアの騎兵一個中隊が駐屯していたので、そこを逃れて2人は営口に移る。ここで戦争勃発のウワサを聞きつけた日本人が多数引き揚げてくるのを見る。
明治三十七年一月四日
参謀本部次長男爵児玉源太郎
外務次官珍田捨已殿
瀬川営口領事ヘ左ニ記載ノ主旨ヲ以テ貴省ヨリ
御通達方御取計相頃之度此段及依頼候や在□□瀬川領事ヘ依頼案
今般秘密探偵ノ任務ニ服セシムル為メ
陸軍歩兵少佐江木精夫ヘ陸軍歩兵大尉
土井市之進ノ両名ヲ奉天ニ差□致
候条右両名号□□上ニ関シ諸事
□官ヲ得可□御配慮相煩シ度及□
□□□
追テ前記両名ハ御国人ヘ変装致ス
ヤモ□□□召□念□□□やSegawa Newchwang
陸軍歩兵少佐江木精夫
陸軍歩兵大尉土井市之進 will
be sent to monkden for
military espionage. 兒(?)源
次長 requests you to extend
to themSaid offiersfull
convenience in accomplishment
of Their secret mission.
I may add what he said officers
may possibly disguise(?) as choise.
Kon???
sent Jan. 5 1904 11-45 am
【江木歩兵少佐一名ヲ奉天ニ派遣/明治37年1月4日付外務省外交資料】
先に述べたように、精夫が予備役になって以降、何をしていたかはよく分からない。
さてまたまた話はそれるが、松江豊寿という人をご存じであろうか。この人の伝記映画が2006年に封切られるとのことなので、少しその絡みを書いておきたい。
松江豊寿という人は第一次大戦時、徳島県鳴門にあった捕虜収容所長で、そこには青島に駐留していて捕虜となったドイツ兵が約1000人収容されていた。しかしその収容所は非常に人道的に運営され、捕虜であるはずのドイツ人との交流からパンや工業などの技術や文化が町に拡がり、ベートーベンの第9はここで日本初の演奏をなされることになる。 ドイツ本国でも評判が高く、模範的収容所とまで言われた。日本では『二つの山河』という小説で有名になった。
さてこの松江豊寿大佐、正義感と信念を曲げないことでは有名で、当時二度軍法会議にかけられたことがあるらしい。その1回は明治40年(1907)浜松の第67連隊付少佐であった時代のことである。この時、松江は上官に意見して軍法会議にかけられたが、結果として無罪になっている。しかしこの明治40年といえば浜松の第67連隊が編成された年であり、その時の連隊長は江木精夫中佐なのであった。つまり、連隊付少佐であった松江豊寿が口答えした上官というのは、江木精夫であった可能性が高い。のである。
ただしこの話は遺族による回想であるようで、事実確認ができていない(検証不可らしい)。実際何が問題だったのかはわからない。松江豊寿関係の本でも深くは触れられていないが、松江の信念を語るエピソードとして語られているので、その書きっぷりでは江木精夫に少々分が悪いが、そもそも当時の軍隊組織で上官に反論すること自体問題と言えば問題。
ちなみに江木精夫は長州出身、松江豊寿は会津出身である。
さて話は戻って、千之が貴族院で内務畑の政治家、弟の衷は司法界出身の売っ子法律専門家。精夫は陸軍軍人。栄子と衷が結婚した当時は、衷はすでに弁護士事務所を開設しており、千之は茨城県知事を務めていた。これだけでもかなり強力な家庭であるが、実はこの一族にはもうひとり政治家がいる。衷の甥、というか、実は千之の婿養子なのであるが、江木翼である。
東京都練馬区にある遊園地、豊島園の側に小さな日本庭園がある。向山(こうやま)庭園という名のその庭園は、閑静な住宅街の真ん中にありながら鯉の群れる池と豊かな緑を備えた庭を持つ本格的な純和式の家屋で、現在この庭園は練馬区により管理され、母屋と茶室が近隣区民の文化活動のために一般公開されている。(※10)
この家屋は昭和初期、ライオン首相と呼ばれた浜口雄幸内閣の鉄道大臣の邸宅であった。この鉄相こそ江木翼である。
 |
私は中途の入学者であり、殊に郡内第一の優秀学校へ劣等学校から転学したのであるから、多くの同級生、否下級生からも随分馬鹿にされ、甚しき悪戯の限りをされたものである。或時は、持っていった弁当箱を昼飯時にあけて見ると、飯はなくて土が詰めかへてあったなどは、珍らしいことではなかった。(中略)誰も彼も寄ってたかって、此の弱い者をいぢめたものである。(中略)此の頃は、岩国では未だ士族といふものゝ権威が墜ちていなかった為めか、士族階級の者の平民に対する態度は、可なり傲慢なものであった。【江木翼伝】
しかし恵助少年はそれにくじけず勉学に励み、山口高等学校を主席で卒業、東京帝国大学法科に入学している。少時から神童と呼ばれていたようで、山口高等中学校時代に文学に走っている。翼は晩年まで読書家として知られたが、その遠因はこのあたりにあるのだろう。後の話となるが、翼は柳田国男や国木田独歩らの龍土会に参加している。国木田独歩は子供の頃、一時山口県玖珂郡に住んでいた時期がある。もしかするとその時からの知り合いだったのかも知れない。 龍土会というのは自然主義文学者の集まりで、六本木の龍土軒というフランス料理屋で開かれたためにこの名が付いている(この店は現在でも移転しているが六本木にある※11)。「自然主義は竜土軒の灰皿の中から生まれた」とまで言われ、柳田、国木田の他に島崎藤村、田山花袋、蒲原有明、小山内薫などが参加していた。
その時分は、竜土軒は既に今の新築の洋館になっていて、あの茶屋上りらしい細君がいろいろチヤホヤするようになっていた。自然派の文芸は、竜土会から生まれたなどと世間から言われたので、後には、雑誌記者、新聞記者なども多くやって来て、二十五、六人の大きな会になったことも尠くなかった。
その時分には、片上、前田、吉江君などという人たちも入ってきた。今は政治家で、かつては内閣書記官長であった江木翼君などもやってきた。
【田山花袋/東京三十年】そもそもの起りはかうである。話好きの柳田国男君がをりをり牛込加賀町の自邸で花袋、藤村、風葉、春葉、葵(生田)諸君と、それに自分も加へられて招待された会合があつた。この会には柳田君の学友で、後に派手な政治の舞台に活躍することゝなつた江木翼さんの顏も見えた。それから暫く経ってその会を表に持ち出すことになつて、矢張同じ連中の顏ぶれで、その第一回が麹町英国公使館裏通りのさゝやかな洋食店快楽亭で催された。明治三十五年一月中旬のことである。その時わたくしが肝入であつたといふのは、会場がわたくしの家に近かつたからでもある。
【蒲原有明/龍土會の記】
この当時は、先の千之の言葉にもあるように出身地による藩閥、人脈が大きくものを言った時代であり、地方の若者は先に東京に進出している先輩を頼って上京し、書生として暮らしながら勉強し、職を世話してもらうというのがごく普通だった。おそらく翼もこのケースだろう。翼の在学中の学費は衷が支給していた。衷が官界を辞するかどうかという時期であり、その口利きで、当時栃木県知事であった千之に紹介されたものらしい。千之には秀子という娘がいたが男子には恵まれなかった。翼は明治30年(1897)に大学を卒業すると同時に、茨城県令江木千之の婿養子に入ることになる。また、同時に名前を羽村恵助から江木翼に改める。これは、つらい少年時代にバカにされたことに起因するようで、岩国時代から改名を望んでいたらしい。
翼は当時三井物産に入社を考えていたが、千之の養子となったことにより方針を変更し、行政官を志すことにする。大学卒業と同時に明治30年文官高等試験を受験するが、失敗。翌31年に再チャレンジして見事合格する。
こうして翼は内務省造神宮属を振り出しに官僚の道を歩む。神奈川県事務官を経て明治36年(1903)3月に内閣法制局参事官、翌37年内閣書記官を兼任して記録課長、明治43年(1910)拓殖局部長を歴任している。貴族院議員の養父千之の後ろ盾か、翼には有力者の知人が多い。千之は同郷山口県出身の山県有朋系の官僚政治家であり、翼も長州系官僚の若手有望株と期待され、山県有朋派の番頭、寺内正毅などに可愛がられたようである。特に養父千之の関係する防長教育会の貸費生であった柴田家門を通じて桂太郎との知遇を受け、深く関わっていくことになる。このまま順当に行けば、翼は長州系の官僚政治家としてある程度成功し、安泰な人生を過ごせたかもしれない。しかし翼は敢えて自らそれを拒否する。
ここで明治末期の政界地図を説明しておく。正直言って筆者の手に余るのではあるが、独断と偏見に基いて簡単に記してみたい。
成立期の明治政府は、維新に功があった薩摩、長州、土佐、肥前の四藩の元勲たち、つまり藩閥に牛耳られていたと言って過言ではない。しかし土佐藩は幕末の動乱の中で優秀な人材を多く浪費し、肥前佐賀藩も完全な後発組であり、薩長の後塵を拝していた。現実的に明治政府は薩長閥に占められていたのである。これは初代内閣の構成を見るだけで歴然とわかる。長州6人、薩摩4人、土佐1人、旧幕臣1人という構成になっている。
大隅内閣辞職以後、所謂憲政会の苦節十年が始まって、吾々はありと凡ゆる苦患を満喫した。江木君はその中にあって、同郷の先輩と意見を異にしたゝめ、殊に苦しい立場にたゝれ人一倍の苦心をされたやうである。(中略)総選挙が行われ、私も地方の応援演説に出掛けた。たまたま江木君の郷里山口県へ派遣されて行ったが、到る処反対党に妨害をされ、「国賊」などと悪罵されて、壇上で縷々立往生するやうな苦しい破目に陥入った事もあった。殊に荻などに於ては、官権の暴壓と民衆の激昂にあひ、実に名状し難い妨害を受けた。(中略)郷里の先輩と政見を異にする事が如何に苦しい事であるか、長い間その苦痛を堪えて来られた君の堅い信念と高い見識に只尊敬の念が胸に浮んだのである。
【若槻礼次郎の追悼文/中央公論1932.11月号】
 |
昨年六月、胃潰瘍手術後順当の経過を取り、今春一時恢復したるも、其の後、潰瘍部より癌腫発生し、肝臓にも転移したる為、漸次衰弱を来たし、最近食欲減退衰弱著しく増進し、二三日前より重篤の状態を呈するに至り、遂に本日午後零時五十五分死去せらる。生来の読書家であり、政治家というよりも研究者然としており、広範な知識を縦横無尽に駆使して政治に辣腕をふるった。華はなかったが、その知略と見識をもって、名参謀として政官界の駆け引きに奔走したようである。鉄道警察は彼が鉄道相時代に制定したものであり、日本工業界の発展を目して、鉄道機材の国産化を積極的に推進した。鉄道相としての責任範囲を超えた発想であるが、彼は一旦方針を立てると、周囲の反対を頑として受け付けず、頑迷なまでに実現に向けて行動した。妥協を許さず強引に信ずる道をひた走ったところは、さすが江木衷の薫陶を受けただけのことはあると言うべきか。
昭和七年九月十八日 主治医
【主治医茂在照博士による発表】
人間としては相当親切でもあり、随分人の面倒をも見てゐる、それでゐながら江木のために粉骨しようといふ乾児がほとんどひとりも無かったといふのは、つまりあまりにも江木さんがそう明であって智恵者にありがちな特異的性格−自負と偏狭が結局彼を孤独な人としてしまったと観られてゐる。
【東京朝日新聞/昭和7年9月19日付】
時代は民衆政治の方向に向って流れる。其一面の特長は常識以上に出でない多数の意見が世間の風潮を支配する事である。政治と政治家の平凡化である。此潮流の中に立っては、江木は少しく異彩を放つ。一つの見識を立てゝ、他人が何と云はうとも、それを固執する。その態度が専制的だ。其所に彼の不人気が生れる。だが、それは、日本の議会政治を衆愚の政治に堕落せしめない為めに、彼れが孤軍奮闘してゐる姿とも見られるであらう。翼は闘病生活中、自らの病状を詳しく日記に綴っていた。その日記は、亡くなる二月前、昭和7年7月23日で途切れている。
【馬場恒吾/中央公論1930.10月号】
七月二十三日実直、官僚的と言われた翼らしいといえば、彼らしい末期の筆ではある。
午前十一時半頃梗便、中量
※10:向山庭園
練馬区立向山庭園 東京都練馬区向山3−1−21 西武池袋線豊島園駅下車 徒歩2分。庭園の見学は無料。
※11:龍土軒
東京都港区西麻布1-14-3。この店は二二六事件で青年将校たちが密談した場所としても有名。
※12:朴烈事件
天皇の暗殺を計画して大逆罪で死刑判決を受けていた朴烈が、獄中において同志で恋人であった金子文子と抱擁している写真が政界にばらまかれた事件。犯人の北一輝が治安当局と若槻内閣の責任問題に発展することを期待して行ったと言われている。
さて先に述べたように、江木翼の奥さんは江木千之のひとり娘、秀子という。明治15年(1882)12月10日生まれ、同19年(1886/数え5歳)に東京高等師範学校付属御茶ノ水幼稚園に入園。そこから同21年(1888)同校付属小学校に進み、同27年(1894)日清戦争勃発の年に同校付属高等女学校に入学した。体は弱かったが武家の娘として厳しく躾られたようで、小学校時代からまじめな少女であった。
お茶水小学校に通ひし頃は修身科をこよなく悦び、世の幼児になほざりに聞きすぐすべき世に捨てられし老人、よすがなき孤児の哀なる物語にいたく心をかたむけ、涙ながらに聞きては帰りて父母に物語り、或はひねもす思いわづらひて食を忘るゝことさへありしかば、父母はその健康を害はんことをうれひ、師にこひて修身科を欠席せしめばやと思ひしことさへありき。千之は明治29年(1896)に茨城県令となり、その後栃木県、愛知県、広島県へと転々とすることになるが、秀子もまた一緒に引越、転学を余儀なくされることとなる。千之夫妻は秀子のために(というか、江木家を嗣がせるために)養子縁組を望んでいたが、千之が関係する防長教育会の貸費生であり、郷友会幹事であった瀬川秀男に翼(当時は羽村恵介)を紹介される。当時は翼も岩国出身とのことで、千之邸に招かれたこともあったようだ。これが明治29年(1896)のことであり、翌30年5月6日に同郷の大谷靖夫妻を媒酌として養子縁組の式が滞りなく終了することになる。しかし秀子の厳しいパパ千之は、秀子が高等女学校を修了する4年後まで、江木翼と一緒に住むことを許さなかったとのことである。
【水無月の影はしがき/渡邊世祐】
淡路町に招かれてそして翼もまた同じ頃より健康を害していき、夫の看病もまた必要となってゆく。そんな中、大正12年(1923)9月1日関東大震災に被災する。当時翼と秀子夫妻は赤坂に住んでおり、震災当日も家にいた。千之夫妻は衷と共に軽井沢へ避暑に出掛けていたようである。その震災発生の時、秀子は邸内に掲げる御真影(天皇の写真)を持って避難する。招きつる君が恵を身にしみて行くことかたき我ぞくるしき
いたつきにあらぬ身ならばとく行きて今日の遊びにもれむものかは
もろ人の今日のうたげの楽しさを思ひやりつゝ一人臥すなり
大正十二年九月一日秀子はまず、軽井沢の千之に帰京は遅らせるよう申し送り、真綿・綿入の服を新調して送るとともに、無事であった自邸に訪ね来る親戚や避難者を招き入れ、知らない者も含めて一時は60人もの面倒を見た。衣類や食料や家具などを惜しげもなく分け与え、後に日常生活に事欠く有様であったようである。
朝来晴天なれども風強く温度も高い。朝食前三十分計り散歩をなし、帰来新聞を一読すること例の通り。
十時頃より読書(読書室にて)。十一時半頃に至り軽井沢叔父(註※衷のこと)より手紙来り、過日送りたる詩を訂正し来たる。訂正の処余り面白からぬやうな感を為しつゝ考へ居るところに大震。大分大きいなと思うて天井に懸りたる電灯を見るに、大凡そ九十度の角度を以て運動して居る。座して居る向ふ側に在りたる書物棚の上のサー、ヘンリー、メインの石膏像(穂積陳重先生より貰ひたる物)は墜落し破壊す。ト見ると、其側にありたる真葛香山製の花瓶は小躍をして、今や墜落せむとして居る。此れは落してはならぬと。、座を起ち之を押へることが出来た。斯ることを為す間に、棚より書物は墜落し、外ではガーッと何か落ちる物音すさまじ。是では秀子が大狼狽をやつて居るならんと、ソロ/\勝手の方へ行き見れば、既に室を出で躑躅樹のある所に逃れて出てくる。依て、其処は瓦の飛ぶ処があるから、椎の樹の下に行けと指図す。
余震なるもの引切なしに来るので、余り気持よからず。自分も出て椎の樹の下に行く。必ずや火事起るならんと考へ居たる所、果せるかな火事との声あり。しかるに此処は先づ風上なれば安心と思ひ、さるにても摂政宮は御安泰におはしますやと考へ出しては、一刻も安座できず。とりあへずフロックに着換へ、車を命じて東宮御所への急がす。恰も二時頃なり。到り見るに、途中家根の落ちたる家、塀の倒れたる処など多し。赤坂御所の土塀も大分崩壊して居た。御所の玄関へ入り見ると、ガラスの破片の存せし外、大震を感ぜられたるやうにも見えない。依て仕人に聞くに殿下には宮城に在らせられ、避難せられ、御別条なしとのこと。
地震ニ付御機嫌奉伺従四位勲二等江木翼と書し退出。夫れより下二番町に、加藤子邸(※註:加藤高明)を見舞ふ。既に見舞せる者に小山幹事長、古屋慶隆両氏あり。小山幹事長に党を代表して天機並に御機嫌伺をなすべき様話した。総裁邸よりの帰途、少々の缶詰類を買入れ、一旦帰宅、更に四時頃宮城に天機奉伺をなし、宮内省の次官局長連に見舞を述べて帰宅。此頃、各方面の火事は愈々烈しく、下町一帯は火の海と見えた。殊に宮城東御車寄前の広場から南の方を見れば、黒煙朦々惨まじき有様、言語に絶した。帰宅して見れば、椎の樹の下に夜を過ごすの計も出来て居た。余震は三分五分毎にやつて居る。予は独り例の通り四畳半に入つて寝ることゝした。勿論蚊帳もつりて。但し、雨戸、ガラス戸はしめずに。九時頃に眠に入つたが、夜中幾度か例の余震に目覚まされた。夢は穏かでなかつた。
【江木翼日記/江木翼伝】
大正13年5月10日 第15回衆議院議員総選挙
大正13年6月8日 清浦奎吾内閣総辞職(文部大臣・江木千之)
大正13年6月9日 憲政会加藤高明に組閣命令
大正13年6月9日 憲政会(加藤)、革新倶楽部(犬養毅)、立憲政友会(高橋是清)護憲三派連立を協議
大正13年6月11日 加藤高明内閣誕生。江木翼は内閣書記官長拝命。
大正13年6月27日 江木千之、枢密院顧問官拝命
6月28日江木千之が親任式御礼言上のために参内したあと、秀子を見舞っている。これが父娘が会った最後となった。その夕方には夫翼と談笑できる程度であったが、夜半には容態が悪化、昏睡状態に陥る。翌朝に暫時意識を回復するが、駆けつけた母江木中子に覚悟をもらし、再び危篤状態となる。家族の要望もあって数回食塩注射を行うものの、その甲斐なく、眠るように永眠した。43歳であった。
江木栄子と衷に話を戻す。
栄子と衷の出会いにはこんなエピソードが伝えられている。
それはまだ良人衷が、本郷は元町の小さな下宿屋に転がつてゐた時分のことである。彼はそこから毎日赤門へと通つてゐた。
当時元町附近の下宿を次から次へと廻つて、書生さんたちの汚れ物の御用聞きに歩いてゐた西洋洗濯屋の娘があつた。名を栄ちやんと云ふ。まだほんの肩上げさへ取れない小娘だが、なんとなくあどけない可愛らしいところがあつて、誰にでも好かれる顔を彼女は持つてゐた。即ち元町附近の書生さんたちの話題に忽ち上がつた所以である。分けても後の博士江木衷、当時の帝大法科生江木衷は誰よりも一等此の栄ちやんを可愛がつてゐた。来る度毎に彼は菓子などを与えてゐた。栄ちやんも亦(ま)た従って江木が大好きな書生さんの一人になつて終つた。
これこそ誰あらう、現今社交界の花形の一人たる江木欣々女史其人なのである。
ところが、如何した訳か、ある日限り此の栄ちやんの愛くるしい姿が江木の下宿は勿論、他の下宿にもすつかり見せなくなつて終つた。元町の名物が突然姿を消したのである。さあ大変、書生さんたちの間には忽ち一問題が持ち上がつて終つた。しかも、それは最初栄ちやんが かれ等の仲間に評判になつた時よりも、一層評判になつたのである。中でも江木は一層それを問題にした。
彼は遂に黙過することが出来なかつた。人知れずいろ/\探つて見た。事情は間もなく判明した。彼女の家が弓町であつたから、様子は早く知ることが出来たのである。併しそれは単に栄ちやんの家が商法に失敗して、神田辺へ引越したといふに止まつた。
爾来幾春秋の月日が経つ。江木は学士になつて弁護士を開業した。ある年の新春、東京弁護士会の新年宴会があつた。江木も勿論お客の一人であつた。宴席に侍つた多くの芸妓の中に、江木をして非常に驚かした一人の若い妓があつた。これこそ誰あらう。昔の栄ちやん、今の芸妓栄治其の人であつたのだ――。【明治大正恋の絵巻物/女の世界大正10年1月号】
 |
衷と栄子の結婚した年がいつなのかははっきり分からないのだが、結婚式当日にこんなエピソードが残されている。
先生が駿河台の本邸で結婚式を挙げられた晩、事務所の面々其夜ばかりは御客様気取りで至極行儀ヨク居並んだ。愈々(いよいよ)宴席半に先生の発言でアミダをやる事となり籤に当つた者が買出しに出かける約束の処。花婿殿の先生が其役目に当り。味噌こし笊を提げて門外の焼芋屋に出かけた事があつた。衷は晩婚であったこともあるが、独身時代はその筋でも結構浮き名を流していたようである。尾佐竹猛に「衷は今こそ此夫人を得て納まつて居るが、青年の頃は風流戦はなか/\盛なものであつたが茲(ここ)には其頃の珍聞は見合せて置かう」(『法窓珍話閻魔帳』)との文章が見える。また、衷は栄子と結婚する前、一回離婚を経験しているらしい。明治24年(1891)の「明治貴顕の閨閥一覧」という新聞記事に、法学士外務省参事官江木衷の妻は近藤島根県書記官令嬢であるとの記述が見える。(読売新聞明治24年8月7日)
【嗚呼江木冷灰先生/卜部喜太郎】
新婚の夫妻は神田淡路町に黒塗りの門をいただく豪邸に居を構える。衷は弁護士事務所を蛎殻町から移転していたのである。明治33年(1900)発行の『東京名所図会』によると衷の法律事務所は神田淡路町2丁目7番地にあったとある。事務所と自宅は兼用であった。神田区淡路町は現在でもほぼ同じ場所にあり、当時の2丁目7番地は現在の区画でいうと、秋葉原方面から外堀通りを昌平橋を渡ってすぐの右側、JR御茶ノ水駅から言うと淡路坂を下りきった所で、損保会館があるあたりである。
大正五年の三月二日、あたしは神田淡路町の江木家の古風な黒い門をくぐっていた。結婚当時の淡路町はどんな感じだったか調べてみると、現在の昌平橋は明治33年(1900)に完成している。同時に省電中央線御茶ノ水駅(現在のJR中央線御茶ノ水駅)が開業。大正8年(1919)に江木家を訪ねた記者は須田町駅(市電?)で降りているが、江木家からもっとも近い駅は、中央線万世橋駅である。この駅が開業したのは明治45年(1912)であるが、東京駅に似た赤レンガの大きなターミナル駅だった。駅前には広い広場があり、日露戦争の英雄広瀬中佐の銅像が建てられていた。当時は万世橋駅から須田町界隈は東京の西の中心と目されており、日本橋などに匹敵する賑わいだったようだ。淡路町には現在でも老舗が多く、当時の姿を偲ばせている。ちなみに万世橋駅は関東大震災で焼失し、中央線が東京駅まで開業すると、万世橋駅は不要となり、昭和11年(1926)に駅舎は解体されてしまう。現在の交通博物館がそれである。
旧幕の、武家邸の門を、そのままであろうと思われる黒い門は(中略)今をときめく、在野の法律大家、官途を辞してから、弁護士会長であり法学院創立者であり、江木刑法と称されるほどの権威者、盛大な江木衷氏の住居の門で、美貌と才気と、芸能と、社交とで東京を背負っている感のある、栄子夫人を連想しにくい古風さだった。しかしまたそれだけ薄っぺらさもなかった。含みのある空気を吸う気もちであった。 たそがれ時だったが、門内に入るとすっかり暗くなった。
梅が薫ってくる。もう、玄関だった。
広い式台は磨かれた板の間で、一段踏んでその上に板戸が押開かれてあり、そこの畳に黒塗りぶちの大きな衝立がたっている。その後は三間ばかりの総襖で、白い、藍紺の、ふとく荒い大型の鞘形――芝居で見る河内山ゆすりの場の雲州松江侯お玄関さきより広大だ、襖が左右へひらくと、黒塗金紋蒔絵のぬり駕籠でも担ぎだされそうだった。【長谷川時雨/近代美人伝】
神田というてェとあの須田町というところ電車の停留所がありました。あすこがね、昔は東京一の盛り場でした。と云って、みなさん信用しないかも知れない。本当なんです。衷の弁護士業が軌道に乗るにつれて、豪勢な生活を送るようになっていく。「我儘者で、贅沢者で、食道楽で、飲道楽である」ところの衷らしく、食事、酒、煙草はすべて一流の店から取り寄せる。毎夏には電車を一両借り切り、使用人や専用料理人、書生を引き連れて軽井沢へ避暑に出掛け、毎週東京から鰻を取り寄せたりした。法学博士の夫人として、栄子は学問・諸芸を研鑽を積み、和漢詩、絵画、篆刻、琴、茶道、華道、柔剣道などを、それぞれその世界の超一流の先生を招いて学んでいる。しかしこの習い事に対する熱意も、いわゆる奥様芸の域を越えており、それぞれ玄人はだしの腕を持つようになった。
あの須田町、今、万惣がありますねえ。角ンところに果物屋さんが、あれはありましたよ。それから九段の方から来て交差点の左側に三好野という栗餅屋が出来ましたね・・・あたくしの子供時分に。(中略)
一番始まりはこの須田町。ここン所の交差点の人てえのはなかった。電車が止ってもうぞろぞろ人で一ぱいでした。勿論交通巡査がいましたがねえ、その時分に。まだ信号が出来ちゃいませんでしたが、ここンところは交通整理しなきゃいけないだけ人が通ったんです。あと何処へ行ったって、銀座へ行ったって何処へ行ったって、そんな事はないんですよ。須田町だけはまァひどい通りでした。
【三遊亭圓生/江戸散歩】
「この頃で嬉しいことは主人が嫌ひのために廿年間止められて居たお琴を許されたことでございます。で生田流と山田流と両方いたしてをりますが、組は生田がよく、手琴などは山田がよいと思います。主人の職業はいはゞ勝ち負けを争ふもの、家の中は常に賑やかに、陽気にしてをりませんことにはその日の仕事にひじょうにな影響があると思ひますので、子供のない私は派手な、そして賑やかな妻として仕へてをります。その他大勢の若い人達の元気を一層引きたゝせることはもつと大切なことだと、届かぬながらもこのことは一番心にかけてをります。」【婦人画報/大正8年1月号】
 |
合客は、ある画伯の夫人と、婦人雑誌で名の知れた婦人記者の磯村女史だった。その人が、欣々さんからの使者にたってて、出ぎらいだったわたしを引出したのだった。
(中略)
広い客間の日本室を、雛壇は半分ほども占領している。室の幅一ぱいの雛壇の非毛氈の上に、ところせく、雛人形と調度類が飾られてあった。
「ご覧あそばせ。まるで養子のように、誰も彼も、これは僕のだこれは私のだと、場所を占領して飾りますの、みんな一揃いずつですもの。いまに、室いっぱいになってしまいますのでしょうよ。あんまり見ごとだって、それをまたいろいろの方が御見物にいらっしゃるので――明日は大勢さんをお招き申しましたわ。こんやは、あなたのためにだけよ。」
お雛さまの前に食卓がつくられてあって、みんな席へついた。
「あたくしねえ、給仕は、年の若い、ちいさい綺麗な男の子がすきです。汚ない、不骨な大きな手が、お皿と一緒につきだされると、まずくなる。」
ほんとにその通りの少年が、おなじ緑の服を着て、白い帽子を頭において三、四人出て来た。
キュラソウの高脚杯を唇にあてて、彼女はにこやかに談笑する。
「今晩は、お雛様も御洋食ですの。わざと、洋食にいたしましたのよ、自慢の料理人でございます。軽井沢へゆきますのに連れてゆくために、特別に雇ってある人ですの。」
その、御自慢の料理人が、腕を見せたお皿が運びだされた。
「明日は泉鏡花さんも見えるでしょうよ、あの方の厭がりそうなものを、だまって食べさせてしまうの、とてもおかしゅうござんすわ。」
泥鼈(註:すっぽん)ぎらいな鏡花氏に、泥鼈の料理を食べさせた話に、誰も彼も罪なく笑わせられた。
(中略)
「ええ、ええ、たいへんでしたわ。おいしいおいしいって食てしまってから、たねを明すと、嗽い(註:うがい)をなさるやらなにやら――」
介添えに出ている、年増の気のきいた女中が、その時の様子を思い浮かべさせるように、たまらなくおかしそうにふうッといって、袂で口をおさえた。
食後はもうひとつの広間へ移った。そこはばかに広かった。琴が、生田流のも山田流のも、幾面も緋毛氈の上にならべてあった。三味線も出ている。【長谷川時雨/近世美人伝】
と、いうわけでこの後、長谷川時雨と共に客に招かれた朱絃舎浜子の弾く琴を中心に、三味線やら鼓やらが出てくるわけである。ちなみに長谷川時雨は、この時の様子は、やや揶揄気味に書いている。
それくらい豪勢な生活を送っていたということである。松崎天民の筆によると、
淡路町時代の暮し向きは、明治末から大正の初頭へかけて、月々一千円の支払高に及んだと云われるほど豪贅なものだった。御者、馬丁、門下の弁護士、書生、女中等を合わせて、三十人に近い大家族だった。江木博士の富は、飛ぶように売れた『刑法各論』の謝礼のほかに、法曹唯一の権威として、売れっ子としての収入も、並大抵の数字ではなかった。良人の慈愛に包容されて、間接にのみ世間を眺めて暮らした箱入奥様として、欣々女史は欲して得られぬ物なく、望んで遂げられぬ事と云っては、何一つもなかった。【松崎天民/婦人公論昭和5年5月号】松崎天民の見方は少し厳しすぎるかもしれない。大正時代に社会主義運動が盛んになって、下層社会に目を向けたいろいろな活動がなされるようになってはいたが、それは有名ではあるがごく一部の運動であり、栄子の生活とその考え方は上層階級としての平均的なものではなかったかと思われる。しかも栄子は子供時代にそれなりに苦労を重ねた上に(幸運も手伝って)上流階級に入ったわけであり、その自負はあったと思われる。また、明治期には「不幸な女」「苦労した女」がもてはやされ、美人は「虚栄」「驕慢」「堕落」と見なされていたという。これは現在でも同じかもしれないが。
栄子自身有名になるにつれ、雑誌等へも顔が載るようにになったが、自身も記事もいくつか書くようになっていたようである。当時流行しつつあった女性解放運動にも顔を出すようになり、平塚らいてうの『青鞜』や西川文子らの『新真婦人』などに参加し、その雑誌にもなんどか寄稿している。しかしそれほど深く関わってはいないようだ。大正三代美人に数えられる林きむ子との交流もこの頃のことであり、きむ子が参加していた女性活動「蛙声会」にも参加していた。きむ子はマスコミの槍玉にあがって、あれこれ噂されるのを嫌ったが、栄子はそういう立場を楽しんでいたフシが見える。マスコミの虚報を嫌がる林きむ子に対し、「あなただってかなり華やかな生活といわれたじゃありませんか。野暮なことをおっしゃるな。ある人には当り前のことがある人にはぜいたくに見える。要するにそれぞれが自ら治めるしかないじゃありませんか」と諫めている。【森まゆみ/大正美人伝】
現在でも手軽に読むことができる栄子の文章はないのだが、実はひとつだけ、漫画家夏目房之介が書いた『男女のしかた』(ちくま文庫)に、江木欣々が書いたといわれる『女閨訓』が抄録されている。されてはいるのだが、これがまたすこぶるつきにアヤシいのだ。
このタイトルを見てピンと来たアナタは鋭い。これは女性向けに書かれた房事の指南書、ありていに言ってしまえば「HOW TO SEX」なのである。あえてさわりだけ転載するとこんな感じ。
昔の女は此のことを欲せざる風する事が静淑にして慎み深きものなりと考えたる様なれども、そは最も誤りなり。(略)仮令(註:たとえ)眠りに就きたると雖も静に男根を探りて之を弄び、其の堅く大きくなるを待ちて我から仕掛けて、女陰にくわえ込み、ひしと抱き付きて夫を目覚まさば、夫も亦思いがけざる歓待に驚き喜び狂わん許りに感謝の念を以て之を迎うるは必定なるべし。殊に夫が他の女を想い或は他処に情婦等の出来たる折は一層気を付けて、屡々(註:しばしば)我より持掛け夫の情を取り戻す様につとむべきなり。斯る時には前に述べたる様にして無理にも毎夜の如く乗り掛けて其精液を吸い取り常に夫の精の臓を空にして置く時は夫の心に他の女の想う余裕なくなりて我身のみ可愛しと思う様になるものなり。
【伝・江木欣々/女閨訓】
この文章は伝・明治39年刊とされているが、当時栄子は衷と結婚していて何ひとつ不自由ない生活をしていたし、先に書いた女性活動も始めていた。いまさらこんなことをしているとは考えられないし、そもそもあちこちに見聞きする栄子像にはそぐわない。これは「芸者あがりで大物法学博士をたらしこんで結婚し、また、一時廃娼運動に反対していた」ということから、想像力がたくましい誰かがそのイメージを利用して、栄子の名を騙って書いたものであろう。まあ少なくとも、好き者にはそういう目でも見られていたという証拠でもあるのだが。
さて法学博士江木衷は、当時売れっ子で有名だったよ。とは書いてはいるが、いまいちピンと来ない方もいると思われるので、少しエピソードを追加してみよう。
現在でも経済・法学関係の学術書で有名な有斐閣書房であるが、その経営の基礎は江木衷の本を出版したおかげであるそうだ。有斐閣書房は明治10年(1877)創業であるが、創業者の江草斧太郎は神田一ツ橋に店を構え、商売を越えて学生たちの面倒を見ていたとのことで、江木衷も学生時代に世話になったらしい。その縁で衷は『法律解釈学』を有斐閣書房より発行、続いて出版した『現行刑法汎論』(明20)『現行刑法各論』(明21)がバカ売れし、有斐閣書房の経済的基礎ができたのだとこと。この件は有斐閣書房の社史にもわざわざ章を立てて紹介されている。
ともあれ、有斐閣は江木衷の『法律解釈学』や『現行刑法汎論』、『現行刑法各論』を出版し、それが世に迎えられたことの意義は極めて大きいものがあったといえる。その一つは、卜部喜太郎の指摘にもあるように出版社としての有斐閣の経済的基盤ができたことだろう。二つには、法学書出版の方向がここでかたまり、これにより法学書出版と本格的に取り組むようになったことがあげられる。明治後期から大正時代にかけて衷が尽力していたのは、陪審制度の確立である。陪審制というのは、現在アメリカの法廷で行われているもので、一般から12人の陪審員を選抜して行う裁判制度のことで、映画などでもおなじみのシステムである。衷は花井卓蔵らと司法の民主化を提唱し、この制度を日本に導入しようといろいろな活動をしていた。衷も一般へ向けた陪審制度の啓蒙書を何冊も出している。その結果、日本でも大正12年に陪審法が公布され、昭和3年より施行された。ちなみにこれは普通選挙法より昔の話である。
このように、江木衷は有斐閣の出版活動に決定的ともいうべき影響力をもつことになった(後略)
【有斐閣百年史】
3 陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ムしかし日本においては、戦後になっても司法当局の反対により、制度の復活がなされることなく、未だに停止中のまま、現在に致るまで再開の目処は立っていない。
【陪審法ノ停止ニ関スル法律】
江木衷の評判を客観的に見ることのできる資料はないものかと探していたら、日本弁護士連合会が出版した『弁護士百年』という本を見つけた。江木衷についても1ページ割かれており、「陪審制度の実現には情熱を持ち、明治末年以来、政府に働きかけ、ついに陪審法を実現させたのは江木の努力の賜といってよいだろう」と書かれている。
また、この本に明治44年(1911)の「東都弁護士一覧」が採録されている。これは相撲番付に似せて弁護士を評判順に並べたもので、番付表のど真ん中に鳩山和夫と並んで江木衷の名が見える。その他裏が取れていないのだが、孫文が来日した時に江木衷の家で歓待したなどという話も伝わっている。
社会のあらゆる階層の人々が、江木邸に来訪し、常に門前市をなしていた。政治家あり、弁護士あり、医師あり、新聞記者あり、書家あり、画家あり、俳優あり、実業家あり、稀には「奥さんご気嫌伺いに」などと称して、小使銭をせしめて行く風来坊もやつて来た。又中国等から名士が東京に来た時は、大抵冷灰待我帰軒に招待し歓迎の宴を催した。例えば、孫文や胡瑛などが来日したとき、冷灰盛筵を以て迎えたのである。女史はこれらの諸々の来客を巧みに取り捌き又その招宴を巧みに周旋していた。
【會田範治/近世女流文人伝】
 |
明治42年(1909)、衷は大病に陥り、一時生命のほども危ぶまれたそうであるが、一命を取り留めることができた。しかしそれ以降はあれほどの酒豪が酒を断ち、その変わり点茶会を催した。しかも作古流という流派を自分ででっちあげたところが衷らしい。その会則は、
第一章 喫茶行為の意思表示は、書面又は口頭を以て之を為すことを要す。大正初年(1912)には、今度は栄子が子宮を患い、卵巣の摘出手術を受ける。しかしこの予後が悪かったらしく、栄子は健康を損ねてしまう。時々喀血するなどあったらしく、この後激しい運動などはできない体になってしまったようだ。もちろん衷との子供も望んでいたであろうが、それも叶わぬ夢となってしまう。
第二章 湯は熱度の如何を問わず、茶かたまりの大小を論ぜず、一気に之を呑むべし。但し、目を白黒するを妨げず。
第三章 本法に違ふ者は、独断を以て一月以上二十年以下の訓戒に処す。但し、武士道を知る者は、陪審に依る正式裁判を請求することを得。
【近世女流文人伝/會田範治】
そして大正12年(1923)9月1日、関東地方を未曾有の大地震が襲った。関東大震災が東京を直撃したのである。中でも神田地区は都内でももっとも被害の大きかった地区のひとつであり、神田淡路町の黒門の江木邸も焼け落ちてしまう。江木衷と栄子夫妻はたまたま軽井沢の別邸、遠近山荘に出かけていたため無事であった。一家は牛込区砂土原町3丁目に引っ越して居を構えるが、大正13年頃衷は病を得、その後一年ばかり小康を保っていたようである。
江木夫妻には子がなかったため、どうやらこの頃に養子を迎えたらしい。江木衷の跡継ぎとして迎え入れられたのは、衷の弟精夫の次男、富夫である。
しかし大正14年(1925)4月5日に危篤に陥り、翌6日には医師の手当により一時奇跡的に回復したが、桜がほころびかけた4月8日午後2時30分、心臓麻痺により逝去した。68歳であった。
江木衷博士逝く
欣々夫人も面窶れして
◇…告別式は十二日
数日来危篤の状態にあった法学博士江木衷氏は八日午後二時半牛込区砂土
原町の自宅で遂に逝去享年六十八、夫人ゑゐ子は欣々女史として知られ家
に子女なく家族は養嗣子富夫氏のみである、同邸では午後五時喪を発した
が弔問客で混雑を極はめ約二ヶ月にわたる看護に面やつれした欣々女史は
内閣書記官翼博士夫妻と共にその間を斡旋して憂愁のいろ庭内にみちてゐ
た、因みに告別式は十二日午後一時から二時まで自邸で行ひ谷中墓地に埋
葬の筈であるが危篤の旨天聴に達し特旨を以て勲二等に叙し瑞宝章を授け
られた
【東京日日新聞/大正14年4月9日朝刊】
死亡広告は、兄の江木千之と栄子の連名で、各新聞に出されている。
冷灰江木衷 四月八日午後二時三
十分逝去致候御通知に代へ此段謹告
仕候
来四月十二日午後一時より二時迄牛
込区市ヶ谷砂土原町三丁目十七番地
自邸に於て仏式を以て告別式執行致
候
四月十日 江 木 栄 子
江 木 千 之
衷の葬儀は栄子が一手にひきうけたが、かなり盛大で豪華なものであったらしい。
栄子には実子はなく、多くの書生と手伝いを抱えたまま、46歳で栄子はひとり取り残されてしまうこととなった。沓掛の別荘をはじめ、衷の遺産も多く残されていたため、生活面で苦労することはなかったが、衷という後ろ盾を失ったことにより、華やかな表向きの生活はなくなり、女手ひとつで家を切り盛りしていた。女中の頭数を減らし、書生たちの面倒を見ながら、趣味の世界に無聊を慰めていたようである。
大正十四年に夫君の衷博士に死別れてからは家政整理を弱い女の一つに引受けながら淋しく故博士の菩提を弔つていたが博士の死後間もなく某伯爵が權威をかさにきて結婚を申し込み見事にひじ鉄をくはせたものである
【東京日日新聞 昭和5年2月21日付朝刊】
衷が亡くなったため、栄子は牛込区納戸町に引っ越す。先に述べた通り、江木精夫の子富夫を養子を迎えている。当時は「家」の観念の強い家父長制だったので、これはしょうがないことである。また徴兵制の生きていた時代であり、長男となると徴兵されずに済むため、徴兵逃れとして養子となるケースもあったようだ。跡継ぎがないために養子を迎え入れるというのは、前に書いた江木翼のケースも同様である。
前記したように、精夫が明治42年(1909)に陸軍を退役して以降、何をしていたかはよく分かっていないのだが、富夫は明治22年(1889)に生まれており、栄子の10歳年下である。一時伊藤姓を名乗っていた時期もあったらしい。
富夫は早稲田大学商科に進み、経済の世界を目指す。明治40年(1907)にここを卒業すると、太平生命保険会社(※13)に入社する。太平生命保険は明治42年の創業だとのことなので、ほぼ会社設立と同時に入社していることになる。大正5年から8年(1916-19)にかけてアメリカへ遊学し、帰ってくるなり徴収課長に昇進、大正12年(1923)に副支配人となる。
伯父(父精夫の兄衷)が亡くなったことにより、大正14年(1925)に江木家を継ぐために養子となり、家督を相続する。つまり養子とは言っても36歳なのである。すでに結婚して長男の信敬も生まれている。
翌大正15年(1926)8月に営業部長となり大阪支店長となったが、昭和3年(1928)11
月、天賞堂に専務取締役として迎えられる。
銀座の天賞堂といえば、明治12年に江澤金五郎が創業した宝石・時計商として、まだ煉瓦街であった明治の銀座に燦然と輝いていた名物店であり、夏目漱石の『虞美人草』などにも登場する老舗である。現在でも銀座4丁目交差点に天賞堂が存在するが、江澤金五郎のオリジナル天賞堂が、新本秀吉に経営者が変わって、その名前と事業を引き継いで昭和3年(1928)に創立した店である。扱い品目は、初代と同様当初は宝石と時計を商っている。昭和24年(1949)から始めた鉄道模型の製作・販売の方も有名である。
富夫が入社したのは後者の方の天賞堂である。富夫が天賞堂に招かれた経緯はよくわからないのだが、昭和3年11月の新生天賞堂設立と同時に移籍しており、設立資金がらみの問題なのか、あるいは富夫の腕を見込んで招かれたものであろうか。大正10年(1921)頃9歳年下の酒井みつと結婚しており、少なくとも4人の子供を得ている。
栄子は昭和4年(1929)頃豊島園に家を建てた。先に旧江木翼邸として紹介した家がそれのようだ。養子の富夫は牛込区砂土原の家に残り、栄子ひとりだけが引っ越した。
先に述べたように栄子はたびたびあった再婚の提案も断り、衷の冥福を祈って毎日読経し、衷の遺稿を整理したり、趣味の書画篆刻で自らを慰めるといった尼僧のような寂しい生活を送っていた。ませ子や長谷川時雨など友人との付き合いは続いていたが、千之など衷方の親戚付き合いは疎遠になっていったようである。また、晩年は貯金通帳や印鑑などを安心して預けられるひとも周りにおらず、巾着に入れて常に持ち歩いていたとも伝えられている。
大正初年(1912)の子宮摘出手術の影響で体調も悪く、華美を誇った生活と、後ろ盾となる夫、さらに美しさまでを失った栄子は、その生活に疲れ果て、神経衰弱にかかってしまう。一時は新興宗教の大本教の出口王仁三郎(※14)の道場にも赴いたこともあったらしい。
昭和4年(1929)12月、弟の早川徳次に招かれて、栄子は静養のために大阪を訪問する。この地に2ヶ月ばかり滞在したが、半分以上は病臥していたようだ。
まもなく東京に帰る予定としていた昭和5年(1930)2月20日、久しぶりに体調のよかった栄子は観光がてら住吉大社に参詣に出かけ、帰ってきてから土産物の菓子などをつまみつつ家族と夕食を取った。食事が終わって栄子は二階の自室に下がったが、数刻後、家人が様子を見に階上へ上がってみると、栄子は縁側の鴨居に帯をかけ、自ら縊死していた。醜くなる顔を見られないように、江木家の定紋の入った袱紗で顔を覆い、右手に水晶の数珠を握っていた。
54歳であった。
遺書を認めて辞世の句は「池の面の夕日に映えし紅葉かな」という。
自殺した欣々女史
家族と共に機嫌よく夕飯をすま
して僅か二十分の後には自殺した
【大坂発】自殺した欣々女史は故衷博士の死後非常に健康を害してゐたが、
自殺当日の二十日には家の人と昼飯を共にし早川氏夫人こと子さんや女中
本田とし子の二人と一緒に電車で住吉神社に参拝し、午後三時ごろおみや
げなどを買つて来てソレを食べつゝ「今日はお天気で久しぶりに楽しい思
ひをしました」とさもすが/\したやうな面持であつた、さうして午後七
時ごろには矢張り家人と一緒に楽しげなる晩餐の卓につき、すまして二階
六畳の自分の部屋に引取つたのである、がそれから僅二十分位の後、縁側
の梁にモズリン兵児帯をつるして自縊したものである、なほ遺書もあるが
東京の江木邸から誰か来るまでは一切発表せぬことにしてゐる、因みに葬
儀日取その他のことも未定である
『尼僧のやうな
精進生活がしたい』
江木欣々女史は大正十四年四月夫君衷博士(法曹界の権威、わが国陪審法
の恩人)の死後は牛込区納戸町の自邸で尼僧のやうな生活に入つてゐたが、
昨春市外練馬に数奇をこらした邸宅が出来たので、三月二十一日移り故冷
灰博士の冥福を祈りつゝてん刻や画筆に親しんで淋しさをまぎらしてゐた
大正初年卵巣の手術をして依頼をして以来血落症状を来し時々血を吐
き発作的に非常な憂鬱に陥る事があった、性来賑やかな事が好きだっ
たゞけ博士なき後はしみ/\゛と寂しさを感じ衷はなぜ死んだのでせ
うと側近の人々にもらしてゐた
昨年の半は病床にゐた有様で大阪の早川氏が「気晴らしに来てはどうか」
とのすゝめで□□女中二人を伴ひ大阪へ旅立ったが、その日まで浄土三
部経の紺地金泥の浄書に明けくれを暮らしていゐた、大阪滞在の六十日
間の五十日までは寝てゐた有様で二十日練馬の留守宅を預かつてゐる田
岡氏あての手紙によると
大阪は東京より三度位寒い、月末まで帰る予定だが帰京したら青山善
光寺にお詣りして尼僧のやうな精進生活をしてみたい云々
とあつた、これから想像すれば自殺するといふ事は考へてゐないらしい
欣々女史は衷博士の家督相続人になつてゐたので沓掛には一萬余坪
の宏壮な別荘もあり、公債や株券など夫人名義のもの多數あつたか
ら日常生活は淋しかつたが物質上困る事はなかつた
遺骸は危篤のまゝで二十四日練馬の自邸に運びかへる筈で近親の人四五人
は今朝大阪へ向け出発した
近親の人々は自殺の原因は発作的に憂鬱に陥つたのではないかと見てゐ
る、なほ女史は一面世話好きで女史の手で大学を卒業したものも多く、
学生からは慈母のやうに慕はれてゐた、この連中は今会の各方面で相当
な地位についてゐるものも多く拓務省秘書課長高橋周蔵氏も大学時代か
ら世話になつた一人である
【東京日日新聞/昭和5年2月21日夕刊】
袱紗に顔を包み
悲しい最期
欣々女史の遺書開封
【大坂発】廿日夜、静養のため帰つてゐた里家の実弟大阪市住吉区北田
込町の早川徳次郎氏邸で自殺した江木欣々女史は早川邸の縁側の梁で藤
椅子を踏み台にして錦紗のしごきで縊死したもので、醜くなる顔をみせ
ぬため江木家の定紋の入った袱紗で顔をおほい右手に水晶の珠□をかけ
てゐた なほ廿一日故女史の養嗣子江木富夫氏や女史の恩顧を受けた拓務
省の高橋秘書課長など来阪したので午後十一時から親族会議を開いて書
置きを披いたが、それは巻紙へ
あと/\の事富夫と御相談の上
万事よろしくねがひ上候
徳次郎様御夫婦へ
二月廿日 栄子
とあり、また叔父に当る東京市外中野新町三、七八七の関信利氏夫妻に
宛てた絵はがきには
御親切なる御見舞下され(中略)
当市滞在二ケ月の中五十日も臥
床の身と相成り実に閉口この上
なく候、心身に多少無理を致し
ても帰京致すべく候
更に東京府下杉並高圓寺「高橋京子様」あてで
私今以て病魔閉口にて全快次第
帰京致すべく候
とあるのみで今度の自殺は全く発作的のものらしい、因みに遺骸は廿二
日近親者ばかりで告別式をとり行ひ同夜午後九時を執行のはず
【東京日日新聞/昭和5年2月22日朝刊】春浅し・麗人の
哀しき帰京
欣々女史の遺骸帰る
春浅き廿三日朝九時、今にも泣きだしさうな空もやうの東京駅に一世の
佳人江木欣々女史の遺骸が著いた、八時半の待合室の名刺受には名詞が
うづ高く、九時には二百余名の出迎へ、江木千之夫人や長谷川時雨女史
などの顔も見へる、正九時、貸切柩車から花輪に埋もれて白布に包まれ
た霊柩が早川徳次、同政治、拓務省の高橋秘書課長などに護られて降さ
れる、出迎への人々は目がしらをうるませる、婦人の中からはすゝり泣
きの声がもれる、華かなりし時にくらべて余りにも淋しかつた晩年が今
更の如く人々の胸を打つ、養嗣子江木富夫氏は
実際数奇を極めた一生で父の歿後は淋しいものでした、今日
(廿三日)は練馬の自邸へ帰り廿五日午後一時から二時まで谷中
斎場で告別式を行ひ直に谷中の父の墓所の隣に土葬にする予定
です
と声をうるませてゐた
【東京日日新聞/昭和5年2月24日朝刊】
江木栄子本月二十日午後八
時於大阪死去致候ニ付二十
五日午後一時ヨリ二時マデ
上野谷中斎場ニ於テ告別式
執行致候御通知ニ代ヘ此段
謹告仕候
親戚総代 江 木 富 夫
【東京朝日新聞/昭和5年2月24日朝刊】
華やかであった時代が嘘のように、ひっそりとした死であった。しかしその死後、一世を風靡した麗人が謎の自殺を遂げたということで、新聞、雑誌に数多くの追悼文が寄せられた。冒頭に記したように、ごく普通の主婦にも注目されるくらいに、ある種の「大事件」であったのである。自殺の真相は謎のままで、金銭問題が原因であるとかいろいろ取りざたされたが、上に引用した新聞記事にあるように、神経衰弱からくる発作的な死と見るのが妥当のようである。
栄子の死より7年後に長谷川時雨が異母妹のませ子を訪ねた時、彼女はこう語っている。
「姉は惜い人でしたわ、育て方と、教育のいようでは河原操さん(※15)のようなお仕事をも、したら出来る人だったと思います。
死ぬのなら、もっと早く死なせたかった。あの通りの華美(はで)な気象ですもの。あの人の若いころって、随分異性をひきつけていました。私がはじめて淡路町へいったころは、毎晩宴会のようでした。あっちにもこっちにも客あしらいがしてあって――江木の権力(ちから)と自分の美貌からだと思っていたから。だから顔が汚くなるということが一番怖い、それと権力も金力も失いたくない。それが、震災で財産を失したのと衷(あに)に死なれたのと年をとって来たのとが一緒になって、誰も訪ねて来なくなったのが堪らなかったらしいのです。よく私に、夫に死なれて後誰も来なくなったかと聞きました。お姉さまの周囲の人と、私の方の人とは違うから、私の方は今まで通りですというと、変に考え込んでしまって――財産が少なくなったっていつでも他のものなら結構立派に暮してゆけるだけはあったのですし、今思えば、京都の方へ旅行するから一緒に来てくれないかといいました。そんなこと言ったことのない人でしたが、よっぽどさびしくなったのだと見えて、練馬の宅には離れも二ツあるから、一緒に住まないかとも言いました。二男を子にくれないかともいいました。けれどあんな気象の人ですからどこまで本気なのかわからないので誰も本気で聞かなかったので、あとでは強い人があれだけいったのには、いうに言えないさびしさがあったとは思いましたけれど――
そうそう、よく死ぬのは何が一番苦しくないだろう。縊死(くびくくり)が楽だというけれどというので、いやですわ、洟を出すのがあるといいますもの、水へ入るのが形骸を残さないで一番好いと思うと言いますと、そうかしら、薬を服むのは苦しいそうだね、と溜息をついたりして、変だと思った事もあったのですが、大阪へいっても死ぬ日に、たった一人で住吉へお参詣に行くといって、それを止めたり、お供がついていったりしたら 大変機嫌がわるかったのですって、それから帰って死んだのですが、あとで聞くと、住吉は海が近いのですってねえ。」
【近代美人伝/長谷川時雨】
さてその後の江木家の消息を簡単に見てみる。
養子となった江木富夫には、妻みつと4人の子供がいた。それぞれ昌子(大10)、信敬(大12)、糸子(大正15)、俊二(昭和4)という。富夫は天賞堂で代表取締役まで勤め上げたらしいのだが、昭和17年の『大衆人事録 東京編』(東京秘密探偵社)を見ると、肩書きが「東工輪業(株)社長」「関東州興業(株)取締役」となっている。東工輪業は初期の国産自転車製造会社であり、関東州興業は旧満州国にあった化学会社で、アルコール混合ガソリン(戦争に向けてガソリンを節約するため)の研究などもしていたらしく、第二次戦争期に国策に沿った事業を経営していたものと思われる。
この文章は基本的に文献調査のみに頼っているので、まあ、このくらいが限界だろうと思っていたのだが、ひょんな所でご子孫をみつけてしまった。
信敬は、というか、おそらくまだご健在のことと思われるので呼び捨てにし難くなってくる。江木信敬氏は京都大学法学部を卒業し、現在は退いておられるようであるが、三菱倉庫株式会社に入社、そこで会長まで勤められたようである。
江木俊二氏は、こちらももう一線を退いておられるようだが、日本興業銀行に入社、最近まで株式会社味彩の代表を勤めておられたようである。おもしろいことに、俊二氏の長男の名前は「衷」と名付けられている。二代目の衷氏は平成14年現在42歳であることになる。もし万が一このページを見られているようなことがあれば、一報願いたい。家系を勝手に調べまわっていることをお詫びいたします。
富夫は昭和51年(1976)に87歳で亡くなっている。妻みつは平成2年(1990)、91歳で亡くなっている。
※13:太平生命保険
後の日産生命保険。平成9年(1997)大蔵省より業務停止命令が出て物議を醸した。
※14:出口王仁三郎
大正時代の有名な新興宗教家で大本教の教祖。大本教は現在でも続いている。
大正10年に第一次大本教事件で出口王仁三郎が起訴されたとき、衷が弁護した。
※15:河原操
日露戦争前夜に対露情報収集のためカラチン王室へ派遣された女性教師「河原操子」のことか?
ところで、栄子が亡くなったのは静養に訪れていた早川徳次邸であると新聞記事に書かれている。名字は異なるが、栄子の異父弟である。この早川徳次という人、何を隠そう家電大手のシャープ株式会社の創業者、早川徳次(とくじ)その人なのである。地下鉄の父と呼ばれた早川徳次(のりつぐ)とは別人。
さて栄子の母藤谷花子を思い出してもらいたい。
関新平に手をつけられ実家に帰された花子は、栄子を里子に出した後、実業家の早川政吉に嫁いでいた。早川家は旧幕時代から京橋北新堀にあった桝屋という袋物屋を営んでおり、明治9年(1876)には久松町へ移転していた。花子の実家大和屋も袋物商であることから、その縁なのであろう。花子との結婚の頃には、政吉は一閑張りのチャブ台(※16)の製造・販売をしていたらしいが、花子の実家大和屋に縁のあった実業家森村市左衛門のツテでミシンを輸入し、小さな縫製事業を起こしていたらしい。時代の流行は着物から洋装に移っており、その関係であろう。森村という人は、一説によると大和屋の番頭であったというが、おそらくそれは間違い。というのもこの森村市左衛門、旧森村財閥を一代にして築いた森村市左衛門その人であるのだ。
森村財閥は現在のTOTO(旧東洋陶器)、INAX(旧伊奈製陶)、日本碍子、ノリタケなどを擁している財閥グループであり、元々は銀座の袋物屋で後に森村テーラーという西洋服飾を扱う店を開いた。大和屋との繋がりはこの頃のことと思われる。森村はその後、福澤諭吉の薦めでアメリカとの貿易を目指して森村商会を設立、明治9年(1876)ニューヨークに進出する。その縁で福沢諭吉の息子たちや慶應義塾生が渡米留学した際に、この会社が一手に引き受けて面倒をみていたという。
早川政治には前妻との間に彦太郎、静子という一男一女がいたが、花子との間にも二男一女が生まれている。登鯉子、政治、徳次で、末子の徳次が生まれたのは明治26年(1893)のことである。彼らは栄子から見れば異父弟妹ということになる。早川の洋裁業は、おりから始まった日清戦争のために順調に進んだが、その多忙さからか、夫婦共に肺の病いに倒れてしまう。
栄子は実親も知らないまま里子に出されており、花子の子供たちもまた養子に出され、この兄弟らはお互いの存在を知らぬまま育っていくことになる。
早川徳次は早川政吉と花子の末子として、日清戦争の前年明治26年(1893)11月3日に生まれているが、両親が病床に就いたことにより、花子に縁のあった深川東大工町の肥料商、出野源八家に養子に出されることとなった。徳次はまだ1歳11ヶ月であったため、自分の本当の両親を知ることはなかった。出野家ではまもなく源八と養母らんが離婚し、後添いとしてすえが入る。この頃には出野家は落ちぶれていて、肥料商とは名ばかりで、その実は賃貸しのリヤカーで魚の臓物を集めて納めるといった日銭稼ぎで、食事にも事欠くような相当困窮した生活だったようである。
これまで江木栄子の周囲で観てきたような富裕階級の世界とは全く異なり、徳次はまったく悲惨な貧窮生活の世界に住んでいた。
養父源八は酒飲みでろくに仕事もせず、後妻のすえはなにかにつけ徳次につらくあたり、徳次に仕事を押しつけて自分は遊んでいるような継母で、とにかく徳次につらくあたった。徳次は学校に上がる前から家計の助けに夜更けまでマッチ箱のラベル貼りに精を出し、小学校に入学はしたものの家計が苦しく、2年生で退学させられてしまう。
継母は2児を産んだが、徳次へのいじめは続き、彼は実質10歳に満たない年齢で一家5人を養うだけの生活費を稼がねばならないという悲惨な生活を強いられていたのである。
しかし近所の井上という盲目の女行者が徳次の状況に同情し、本所北二葉町にあった錺(かざり)職人の坂田芳松のところへ奉公に出すよう両親を説得する。明治34年(1901)9月15日のことである。
錺職というのは江戸時代にはかんざしの細工などをしていた金属加工業の一種だが、この明治末期には大流行したこうもり傘の石突きや付属品などを手作りしていた。徳次は9歳のときから7年7ヶ月の奉公に出ることになったが、その間に主人が鉛筆製造業に手を出して失敗、事業が傾いて先輩奉公人がみな逃散するなどという事件もあったが、徳次は義理堅く(実家に帰りたくないというのもあったろうが)7年7ヶ月の丁稚奉公と、1年の御礼奉公を勤めあげる。この間も継母は毎月のように金をせびりに来て、徳次の小遣い(奉公中なので給料はない)を巻き上げていたそうだ。
徳次はここで穴の不要なベルトのバックル「徳尾錠」を考案する。ベルト穴がなく、コロでベルトを挟んで固定するあのベルトのことである。これが大当たりし、徳次はちょうど年季が明けたこともあり、年号が変わった大正元年(1912)、本所で独立する。徳次19歳の時のことである。
尚、徳次はのちに成功した後も、この坂田夫婦の面倒を見続けている。
早川徳次は奉公に出る前から、出野源八は自分の実父でないことに気づいていたが、実親が誰かまでは分かっていなかった。しかし大正3年(1914)頃、出野家に立ち寄った際にに実親早川家の事を知り、日本橋鉄砲町の浅田という親戚経由で姉登鯉子、兄政治と再会を果たす。すぐに母親違いの彦太郎、静子とも会うことになるが、この時には両親の早川政吉、花子は既に亡くなっており、再会を果たすことはできなかった。再会当時、登鯉子は小林家に嫁いでおり、三越百貨店で貴賓接待係を、政治は自転車業に。彦太郎は母親方の白石家を継いでおり、日本橋の綿糸問屋へ。静子は大倉組の建築技師後藤に嫁いでいた。そしてこの頃徳次は文子と結婚している。
その後まもなく(おそらく翌大正4年)、徳次は異父姉にあたる江木栄子とも再会を果たすこととなる。
栄子は明治30年(1897)頃に江木衷と結婚したが、養子関係が複雑で、自分の戸籍がどうなっているのか分からなくなっていたらしい。そのため自分の出自を調べているうちに、自分の実父が関新平であるを知り、同時に腹違いの妹ませ子の存在を知ることになる。栄子とませ子は明治33年(1900)頃に再会、というか、初めて顔を会わせるが、この頃には早川花子も亡くなっていたため、これ以上の調査は難航したのであろう。その後しばらくたってから、早川に嫁いだ花子に子供(栄子から見ると異父兄弟)がいることが突きとめられる。
この調査は当時有名だった岩井三郎探偵事務所(※17)に依頼して調査されたものだが、岩井三郎は大正4年(1915)頃に早川徳次兄弟を見つけ出し、栄子と徳次は初対面することになる。ませ子との再会から10数年後、栄子35歳、徳次22歳の時のことである。
栄子が調査を依頼した探偵であるが、この岩井三郎という人は日本の私立探偵の草分け的存在であり、一時江戸川乱歩が入社を夢見ていたという名門である。元警視庁の刑事であったが、明治28年(1895)に私立探偵として独立。「花王歯磨き密造事件」や「古河炭鉱詐欺事件」で活躍し、「伊達事件」(※18)で弁護士界や上流階級に名を広めた。大正2年(1913)には「シーメンス事件」(※19)を調べ上げ、日本海軍の汚職事実を明るみに出した。雑誌連載小説のモデルとなり、伊達事件を小説化した檀一雄(※20)の小説『夕陽と拳銃』(のち映画化)にも登場、全国にその名を轟かせた。
余談だが明智小五郎や祝十郎(月光仮面)のモデルとなったのもこの人だそうだ。
ところで江木栄子と早川徳次の再会シーンはこのようであったと言われている。
馬車はやがて江木家に着いた。
(中略)
もと、木造の昌平橋がかかっていたたもとのところだった。
昔の旗本屋敷そのままに、黒く重い木の、どっしりとものものしく冷たい屋敷門のある古風な構えで、その門の柱には江木法律事務所と書かれた大きな表札がかけられてあった。
馬車は門をくぐって、玄関で三人(註;徳次、政治、登鯉子)をおろすと、邸内の馬屋のほうへ走り去った。
「いらっしゃいまし。奥様がそれはもう、お待ちかねでいらっしゃいます」
数人の書生たちや女中たちに出迎えられて、表玄関から、等身大の仁王像や仏像が幾体も立ち並べられてある、うす暗い、ちょっとお寺のような感じのする広い廊下を、左手の洋風の客間へ案内された。
天井からきらびやかなシャンデリアの下に、写真どおりの欣々女史がすっくと立っていた。
「おまえが政治、おまえが徳次。それから、あなたが登鯉子ね。よく来ておくれだったね」
「はい」
「登鯉子さん。あなたには三越でよく知っていたのに、あなたが妹だなんて」
「ねえさん」
登鯉子はもう泣いていた。
欣々は徳次より十七歳年長のはずだから、ちょうど四十歳。
新しい型の束髪に結い、すそ長に着物を着ながして、そのうえから流行の紫色の被布を羽織っていたが、その胸からふさのついたひもが長くちらちらとたれていて、おまけに両腕にはまばゆいばかりのダイヤを散りばめた腕輪が光っていた。
(中略)
「みんな、突然で、おどろいたでしょう。わたしが、あなたがたのねえさんなのよ。おなじおかあさんのおなかから生まれた兄弟姉妹なのよ。こんなにたくさん、妹や弟たちがいたなんて。わたし、うれしい。きょうはわたしの生涯で、もっともうれしい、しあわせな日だわ」
にこやかにほほえんではいたが、ふっと欣々の目にも涙がわくようだった。
ひどくかおりのいいお茶と、和菓子が運ばれてきた。
「さあ、話してちょうだい。みんなそれぞれのことを。そうね、とくに、みんながそれぞれ知っているおかあさんのことを。残念なことだけど、わたしにはちっともおかあさんの記憶がないの。知りたいわ、とっても」
気おくれがして、三人が黙ったままでいると、
「遠慮しないでいいのよ。そう、わたしからわたし自身のことを話すわ。そうしたほうが、みんなも話しやすいだろうから」
あるいは、と想像していたように、権式高くはすこしもなかった。はっきりとものをいい、まるでその母のように美しかった。
隠しだても、すこしもしなかった。ときおり、軽いユーモアもまじえて、関の家に生まれてそれからそれへとたどった自分の道筋を、気さくにたんたんと語った。
(中略)
「関にも、これはおかあさんがちがう妹がいるの。それが不思議ねえ、おなじこの淡路町の、やはり江木っていう写真館にとついできているのよ。こちらの江木の家とはぜんぜん縁つづきでもなんでもないんだけど。でも、親しくつきあっているわ」
(中略)
「お客さまみなさま、おそろいでございます」
やがて、執事がしらせてきて、また仏像の立ちならんでいるうす暗い黒光りのする広い廊下を、奥庭に面した客室へ導かれた。
建物は和風だが、そこも二十畳ばかりの洋室になっていて、二基のシャンデリアの下、まっしろなテーブルクロスの上には祝宴の用意ができており、来客の顔ぶれを見て徳次はおどろいた。
尾崎行雄(※21)、花井卓蔵(※22)、碓井竜太(※23)、磯辺四郎(※24)…雑誌新聞その他の写真で見知っている政界官界の、知名の士ばかりである。
尾崎テオドラ夫人も(※25)いたし、博士の甥の江木翼もいた。
洋式のフルコースの晩餐だったが、徳次は戸惑ってばかりいて、落語か講談のように、登鯉子のするしぐさどおりにまねた。
【石浜恒夫/遠い星】
これは石浜恒夫が書いた早川徳次の伝記小説である。徳次本人へのインタビューを元に書かれているらしいので、基本的な事項は押さえてあるようであるが、どこまでが真実なのかはよく分からない。後に書かれた徳次本人の筆によると、次のように書かれている。
十九年ぶりに順次、これらの兄弟に会ったわけだが、奇談というのはさらに別の姉が出現してきたことである。「私立探偵岩井三郎」という名刺の人が突然私の工場に来て、その姉すなわち江木欣々に会えというのである。母親花子は早川へ嫁ぐ前、愛媛県令関新平に嫁して一女栄子をあげたが、故あって実家に帰った。栄子は数奇な運命の下にあったが、後、法学博士江木衷に嫁し、雅号を江木欣々といった。彼女は明治大正期の社交界の花形として存在していたが、われわれ三人のことを知ると直ちに岩井探偵をよこしたのである。江木家へ三人の兄妹が初訪問した日には、黒塗りの二頭立て馬車が迎えに来て、尾崎行雄、花井卓蔵、碓居龍太など知名の人々も現われて、われわれは披露された。まばゆいばかりはなやかな姉の生活だった。再会後の早川徳次は栄子を慕い、なにかと気に掛けていたようである。天涯孤独と思われた身に、17歳年上の姉の存在は、母親がわりに映ったのかもしれない。夫江木衷を亡くしふさぎがちになった栄子を大阪に誘ったのも徳次である。結局そこで自殺することになるのだが、栄子の遺書を見ても、この、数十年を経て初めて会った姉弟は信頼しあっていた事が分かるであろう。
【早川徳次/私の履歴書】
さて早川徳次は大正4年(1915)、19歳の時に早川式金属繰出鉛筆(エバー・レディー・シャープペンシル)を発明する。現在のシャープ・ペンシルである。株式会社シャープの「シャープ」は、シャープ・ペンシルの「シャープ」だったのである。
徳次は震災ですべてを失った後、大坂に移って再起を図り、早川金属工業研究所を設立する。琴子と再婚し、大正14年(1925)に日本で初めてラジオ受信機の量産に成功、その後世界で始めて電卓を売り出す、液晶など、その後のシャープの大躍進はご存知の通り。自分を不幸な養家から救ってくれた盲目のおばさんに恩義を感じ、全盲者の作業場を立ち上げたり、ボランティア活動も指揮しつつ、昭和55年(1980)に亡くなっている。
以上で江木姉妹小伝の第一部「江木栄子編」は終わりである。が、まだ目を通してない資料もまだある。しかも江木千之と翼の伝記があるのだが、いーかげんにしか目を通していないという事情はあるが、しかしまあそれは、また読んだ時にでも改稿することとしたい。
これが世界的ヒットを飛ばし、徳次は兄政治と早川兄弟金属工業を立ち上げる。徳次は大正11年(1922)病に倒れるが、栄子の奔走により一命を取りとめるといった事件はあったものの、会社もどんどん成長していき、本所林町の他に、押上・亀戸にも分工場を設置し、プライベートでもひろ治と克己という2児をもうける。
不遇な少年期を経てやっと順調な人生を歩みかけたところで、大正12年(1923)の関東大震災である。栄子も家を焼け出されたが、徳次は自宅家屋はおろか妻子まで失ってしまう。また、弱みにつけ込んで借金返済を迫る日本文具株式会社に対し、シャープペンシルの製造機械と権利一切を渡してしまい、それこそ裸一貫に戻ってしまう。この問題がまた後日こじれた時は、昭和2年の日本文具との訴訟においては、江木衷門下の大塚弁護士を代理人として立てている。
※16:一閑張り
「江木姉妹小伝2」へ続く>>
竹細工等に和紙を重ね貼りして強度を増したもの。早川政吉はこの卓袱台製造で実用新案を取って、繁盛したらしい。
※17:岩井三郎探偵事務所
昭和52年に株式会社ミリオン資料サービスに合併。
※18:伊達事件
明治42年不良少年グループのリーダー三笠錦三が射殺され、逮捕されたのが貴族院議員伊達宗城(旧宇和島藩主、独眼流伊達政宗の子孫)男爵の令息、伊達順之助と判明し、大騒ぎとなった事件。裁判所は重罪を宣告したが、岩井が7ヶ月かけて事件を調べあげ、伊達少年の正当防衛を立証した。伊達順之助は後に満州に渡り、馬賊として活躍した。
※19:シーメンス事件
大正3年(1914)1月23日新聞外電記事に、ドイツのシーメンス・シュッケルト電気機械会社東京支店社員であったカール・リヒテルが、解雇された腹いせに秘密書類を盗み出し、会社を恐喝した罪で懲役二年の判決をうけたことが報じられた。この恐喝ネタが、同社から日本海軍将校らに兵器発注関係で贈賄の事実であった。海軍による調査の結果、その他イギリスのヴィッカースからの収賄を受けて戦艦金剛を発注した事実が明るみに出て、世論や議会を巻き込んで大騒ぎとなり内閣は倒壊した。岩井三郎が調べ上げ、野党議員に
渡した証拠が決定打となったという。
※20:檀一雄
一番有名な作品は『火宅の人』。関係ないが、この人の娘が女優の檀ふみ
※21:尾崎行雄
尾崎咢堂。憲政の神様と呼ばれた政治家で、民主政治の確立を目指して活動した。
※22:花井卓蔵
中央大学で江木衷の教え子であった弁護士。「罰せんがために罰するのにあらずして、救わんがために罰するなり」と言って常に弱い側に立って弁護活動を行った。衷と共に陪審法確立に寄与した。
※23:碓井竜太
医者らしいがよくわからない。
※24:磯辺四郎
この人も弁護士。
※25:尾崎テオドラ夫人
尾崎行雄の2番目の妻で、日英のハーフ。
白石某 |―白石彦太郎 |―後藤静子 早川政吉 | 文子 |―小林登鯉子 |―[冫+煕]治 |―政治 |―克己 |――――――――――――徳次 | |―住江 | 琴子 | | 卯作 | |――翼 | 羽村ゆみ子 | | |―芳郎 | 西田明則―中子 | | 江木繁憑―俊敬 |――秀子 | |――――千之 | | | | 近藤某 | | | | |――――衷 | |―精夫 | | 田村糸子 |――富夫(養子) | | |―昌子 | | |―信敬 | | |―糸子 | | |―俊二 | | みつ子 藤谷花子 | |――――――――――――栄子 関迂翁 | | |――関新平 有吉男 |―清英 | 関場不二彦 ? | | |―――――――悦子 | | |――藤子 | |――――――――――――ませ子 和気子 | | 五十川義路 | | |――――――――――――道(政) | | | 福原与曽八 | | | | |――藤右衛門貞雄 | | | | |――惣五郎修齋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |―――――――江木繁太郎鰐水 | | | | |――男 | | | | |――千之 | | | | |――健吉 | | | | |――高遠 | | | | |――――――江木保男 | | | |――松四郎 |――――定男 | | |――信五郎 鶴田蝶子 | | | | |――才介(陶叔) | | 藤井繁 | | | | 河合絹子 | |――義集 |―基 | ? |――義則(周圭) | |―――――――――亀(敏) |――左武郎(訊堂) ?