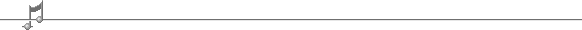 ★タリスといえば「エレミアの哀歌」、「エレミアの哀歌」といえばタリス。
もちろんタリスは他にもいっぱい曲を残しているし、「エレミアの哀歌」は
いろいろな作曲家が手掛けている。しかしこの組合せが最強であることは、
下に紹介したCDを聴いて頂ければ理解してもらえるはず。この曲の教義的な
解説は各CDのライナーノーツに記載されているし、
lamentations(by Early Music FAQ)
にもまとめられているのでそちらを参照されたい。
★タリスといえば「エレミアの哀歌」、「エレミアの哀歌」といえばタリス。
もちろんタリスは他にもいっぱい曲を残しているし、「エレミアの哀歌」は
いろいろな作曲家が手掛けている。しかしこの組合せが最強であることは、
下に紹介したCDを聴いて頂ければ理解してもらえるはず。この曲の教義的な
解説は各CDのライナーノーツに記載されているし、
lamentations(by Early Music FAQ)
にもまとめられているのでそちらを参照されたい。私の一番気に入っているのがこれ。まだポール・ヒリアーが在籍していた ころのもの。原調。男声のみ・各パート一人ずつで演奏されている。 小人数で歌われることによって曲の輪郭がくっきりと浮かび上がり、 このアンサンブルの持ち味である精密な音作りによって完璧な和音を 聴かせる。そういったテクニカルな面もさることながら、全体を通じる なんともいえないアイソレーションと荒涼感がたまらない。とくに「II」 のラストは感動的(;_;)。彼らの演奏スタイルが曲に非常によくマッチして いるように思える。ジャケットのモノクロ風景写真のセンスも○。 私のCDコレクションの中にあってベスト5に入る愛聴盤。密閉されたノイズの 入る余地のない空間で聴きたい。
こちらは混声で最上声部を女声が担当し、短三度ピッチを上げての演奏。 各パート二人ずつということもあって和音に厚みがある。この曲を混声で 歌うのは和声的に難しい面もありそうだが、タリス・スコラーズの演奏は 全く違和感を感じさせない。女声が入っている分だけ明度が高くなった 感じであり、ヒリヤード・アンサンブルのそれとは創ろうとしている音楽が 明らかに異る。この曲の魅力を別の側面からあぶり出す好演。ところで なぜか録音レベルが他のGimellのものと比べてもかなり低く、結果的にS/N比が 悪くなってしまっているのは残念。
ポピュラー音楽をも手掛けるキングズ・シンガーズによる演奏で、構成は 最上声部が2人である点を除いてヒリヤード・アンサンブルと同一。 原調だがこちらはよりステージ感覚で歌われている。発音や息使いが明瞭に 聞き取れるため、実際に演奏する際の良い手本になる。他の演奏に比べると、 低声部でちょっとヴィブラートがかかりすぎている感じがしないでもない。 これは1977年の録音(EMI)だが、少し前に下のような盤が出た。
新生キングズ・シンガーズによる1994年の録音(BMG)。残念ながら未聴。
現代カウンターテナーの祖、アルフレッド・デラーのアンサンブルによる演奏。 やはり原調で構成はヒリヤード・アンサンブルと同じ。古い録音なので音質的 には満足できるものではないが、切々と訴え掛けるような演奏には心打たれる ものがある。一緒に収録されているグレゴリオ聖歌を折り混ぜたモテットも いい味を出していてなかなか聴かせる。最近日本でも再発売され安価で提供 されるようになったので、店によっては割引を考えると輸入盤を買い求める より安く入手できる場合あり。
この盤は未聴のためコメントできないが、タリス・スコラーズ同様混声と いうことでピッチを短三度上げて演奏されている模様。おそらく各パート 3人以上で歌われているだろうから、より豊かなサウンドが期待される。
ナクソスで活躍するオックスフォード・カメラータによる演奏。これも未聴。 聞くところによると今世紀初頭に作られた実用譜を用いているらしい。他の 混声アンサンブル同様短三度上げられているだけでなく、上2声までを女声が 担当し、第3声はハイ・テノールが歌っている模様。この盤にはタリス以外の 哀歌も含まれているので、近々購入する予定。入手次第コメントします。
ポール・ヒリアーによる混声での演奏。1996年現在では最も新しい録音。 残念ながら未聴。
上記の他、プロ・カンツォーネ・アンティクァ、キングズ・カレッジ聖歌隊、 タヴァナー・コンソートなどの演奏を現在CDで聴くことが出来る。
![[back]](../back.gif) Back to The Great Harmony of Medieval and Renaissance Index
Back to The Great Harmony of Medieval and Renaissance Index
![[E-MAIL]](/~tallis/button_mail2.gif) tallis@cc.rim.or.jp
tallis@cc.rim.or.jp